兵庫県立粒子線医療センター
ニュースレターNo.20
March 2005
CONTENTS
■□ 患者にやさしく、速やかな社会復帰を可能にする粒子線治療
■□ 炭素イオン線治療開始とより良い医療のために
■□ 炭素イオン線治療について
■□ 陽子線治療の現状
■□ 保守ネットワークの開設について
■□ 医療事故防止への取り組み
■□ セカンド・オピニオンの実施について
■□ 第4回病院運営懇話会を開催
■□ 陽子線治療にかかる高度先進医療の承認について
■□ 二胡演奏会開催〜「花の季節に向かって」〜
患者にやさしく、速やかな社会復帰を可能にする粒子線治療
名誉院長 阿 部 光 幸
当院は、本年4月で開院5年目を迎える。前のニュースレターでも述べたように、私は当院の基本理念の第一に「がん患者の速やかな社会復帰を目指す」ことを掲げた。その理由は、粒子線(陽子線、炭素イオン線)治療の最大の特徴は、がん病巣を集中して照射できるので、充分な腫瘍破壊線量を安全に投入でき、したがって、放射線に弱い粘膜の被曝がどうしても避けられない胃がんや大腸がんを除けば、がんを切らずに治すことが可能だからである。
問題なのは、粒子線を発生するには大型の加速器を要するので、治療費が高額(約300万円)にならざるを得ないことである。しかし、比較的早期のがんを治療対象にすれば、粒子線治療だけで後腐れなく治癒に導くことができる。つまり、何時までも病院と縁が切れないといった、いわば間接経費が殆どなくて済むのである。このことは日本の医療経済にとって歓迎されることであろうし、また速やかな社会復帰が可能になれば、家庭の経済にとっても大きなメリットになるはずである。ちなみに、陽子線の一般治療を開始した平成15年4月から平成16年11月まで452例治療したが、入院患者の場合、1人1日当りの投薬料は平均145円にすぎず、また治療終了から退院までの在院期間は平均2.4日という短さである。退院後、多くの患者さんが間もなく社会復帰しておられるのを見ても、第一の理念は実現しつつあると思っている。
次に、第二の理念として「病院らしくない病院にする」ことを掲げた。そのため、施設全体をリゾート風の建物にしてもらった。患者さんの不安や怖れを少しでも和らげ、リラックスした気分で治療を受けられるようにするためである。多くの方々から病院臭が少なく快適な雰囲気であることに感心してもらっている。当初はハード面で病院らしくない病院を目指したのであるが、ソフト面でもそのようになってきたことに驚いている。というのは、患者さんの多くは日常の服装で過ごしておられ、酸素ボンベや輸液セットを引きずる方もいないので、病院のイメージが殆どないからである。その原因は、当センターの基本方針として限局性の原発がんを治療の対象にしていることと、粒子線治療は苦痛が少なく、患者さんにやさしい治療だからである。こうしたことから、近くのゴルフ場に連れ立ってプレイに出掛ける方々をよく見掛ける。退院時、治療の感想を聞くと、治療に来たのかゴルフをしに来たのかわからないと苦笑する人や、こんなことでがんが治るのか心配と言う人など、従来のがん施設にはない和やかな雰囲気がここにはある。施設内には囲碁好きの患者さんの寄贈による碁盤があり、時々トーナメント戦が行われる。私も誘いを受けるが、負ければセンターの名誉に関わるし、さりとて医者が患者を打ち負かしても誉められたことではないので、私の立場は微妙である。それはともかく、私が医者と患者の垣根が取り払われた時間を共有しながら碁を打つことなど、今まで考えもしなかったことである。また、患者さんの心のケアとして時々映画会を開いているが、一番人気の高いのは時代物のようである。時には患者さんの企画によるミニコンサートが行われるなど、私のこれまでの医療人生で想像もしなかったようなことを経験している。
開院以来、私は常々病院のスタッフに「病気ではなく病人をみよう」、「心身を共に癒す全人的な治療をしよう」と言ってきたが、それが今まさに実現されようとしている。それと共に、がんの早期発見、早期粒子線治療がシステムとして構築されれば、日本にこれまでのがん治療とは異なる治療形態、即ち、上に述べたような「明るい雰囲気の中で苦痛が少なく、社会復帰の容易ながん治療」という新しい治療形態が生れることは間違いないと考えている。
院長 菱 川 良 夫
当センターは2001年に開院しましたが、粒子線治療装置は、販売されていない装置であったため、すぐに一般の診療には使えませんでした。一般診療のためには、医療用具としての厚労省の承認を必要とします。そのため陽子線の臨床試験を2001年に行い、結果を申請しました。2002年には、炭素イオン線の臨床試験を行いました。2002年末に陽子線治療装置としての承認を得ましたので、2003年4月から陽子線の一般診療を開始しました。炭素イオン線は、陽子線の承認後に申請し、2005年1月に承認され、粒子線治療装置として認められました。
したがって、いよいよこの3月から、粒子線治療装置としては、陽子線、炭素イオン線の2種類のビームを使用できるようになります。当センターの方針としては、それぞれのがんに向いたビームを使用します。1種類のビームですと、全てのがんに対して、使用できる唯一のビームで治療せざるを得ません。2種類を持っている強みで、どこよりも良い粒子線治療が実現します。現在このような治療ができるのは世界唯一です。今まで以上に誇りを持って働ける事になります。また炭素イオン線では、1日ないしは2日での治療が肺がんや肝がんでは可能になります。ただ粒子線治療可能な肺がん、肝がんであっても全てにこの短期日の治療が可能になるわけではありません。慎重に検討を加えて早い時期にこの治療法を立ち上げます。
一般診療を開始してからの2年弱で、530名を超える患者さんを治療してきました。山の上にある病院であるため、安全を第一として厳格な治療基準を専門家の先生たちと共に作り運用してきました。ただ治療基準にはずれても、御本人に粒子線治療を是非受けたいという強い希望があり、技術的にできる可能性がある場合に、粒子線治療開始当初は誰も本当の意味での粒子線治療の専門家でないため、治療方針検討会議を立ち上げ、そこで十分検討を加え、受け入れをしてきました。2003年度の180名の患者さんで治療基準にあっていた方は8割です。この方たちは、95%が再発せずに元気にされています。一方、治療基準に合わなかった2割の患者さんでは、再発していないのは70%ですが、治療基準外である事を考えると非常に高い数値です。もちろん、治療後の経過期間が長期になる事でいずれの数値も下がる可能性はあります。ただ、多くの局所がんの治療成績で再発するのが1年以内という事を考えると、高く評価できるのではと自負しております。
2年間の一般診療の経験から、患者さんはできるだけ早く治療を受けたいという強い気持ちがどなたにもある事を痛感しました。そこで、受け入れ体制を見直し、新年度から新たな受け入れ体制で行います。
大きな変化は、Faxでの申込を成人病センターから当センターに変えます。一般診療開始時には、粒子線治療を安全に確実に行う事に当センターの医師は従事しており、申込Faxに対する検査や受診日などの決定は、成人病センター放射線治療医の協力によりました。2年間の経験から、少し余裕が出てきましたので、申込Faxに対する対応も可能になりました。この2年間での全国一の前立腺がん放射線治療数の経験から、前立腺がんについては、申込後直接当センターに来ていただく予定です。他のがんについては、原則、成人病センター放射線医療室受診となりますが、海外を含む遠方の方や成人病センター同様に高度ながん治療を行っている各地のがんセンターや大学等からは、直接の受け入れもできるようにします。この様にする事で、患者さんの願いである早い治療開始の実現を目指します。
ただ患者さんにとっては、従来とあまり変更はありません。成人病センター放射線医療室に電話(078−929−1339)をしていただき申込用のFax用紙を手に入れるか、当センターのHPから申込用Fax用紙を手に入れて下さい。主治医の先生にお願いをして記入の上Faxして下さい。前立腺がんの場合は、当センター医師が診察日を患者さんに指示します。他のがんでは、申込Faxを見て放射線医療室に指示します。放射線医療室から患者さんに受診日等を電話連絡しますので、従来通り指示日には、資料持参の上放射線医療室に来ていただきます。
この3月には、韓国から初めて粒子線治療を受けに患者さんが来られます。日本人の場合、高度先進医療になりますので、粒子線治療費以外は保険診療が適応され約300万円です。外国人の患者さんでは保険診療の部分が適応されませんので、約400万円になります。でもどうしても粒子線治療を受けたいという強い希望があり、約2月の治療をする事になりました。我々にとっても最初の外国人の患者さんなのですが、当センターでの粒子線治療による楽しい治療を理解していただくようにします。戦争を通じての日本に対する反感を少しでも医療を通じて変えていければと思っております。
炭素イオン線治療について
放射線科長 村 上 昌 雄
今年3月から炭素イオン線の一般診療が開始されます。当センターの粒子線治療は治療基準策定委員会で承認された治療基準に則り、適応を決定し治療を行っています。現在の陽子線治療に加え、炭素イオン線治療の対象疾患を以下に示します。
陽子線 |
炭素イオン線 |
頭頸部 (26回) |
頭頸部 (16回) |
頭蓋底腫瘍
(髄膜腫、脊索腫、軟骨肉腫) (26回) |
頭蓋底腫瘍
(髄膜腫、脊索腫、軟骨肉腫) (16回) |
肺 (10回、20回) |
肺 (9回) |
肝 (10回、20回) |
肝 (8回) |
前立腺 |
|
転移(肺、肝、骨、軟部、リンパ節) (8回) |
転移(肺、肝、骨、軟部、リンパ節)(8回) |
直腸がん術後再発
(37回) |
直腸がん術後再発
(16、32回) |
|
骨軟部腫瘍
(16、32回) |
限局性腫瘍 |
限局性腫瘍 |
1.炭素イオン線治療
炭素イオン線治療は粒子線治療装置により得られた炭素イオン線を用いて、がんに集中して照射を行い、がんの根治をめざす治療法です。重粒子線とは、陽子線や中性子線、重イオン線(炭素イオン線やネオンイオン線など)などの総称ですが、狭義には重イオン線のことを重粒子線と呼びます。
陽子線や重イオン線はブラッグピーク (Bragg peak)という物理学的特徴を有し良好な線量集中性を達成できます。そのため、腫瘍に隣接した正常組織への影響を軽減でき、腫瘍に十分な線量を投与できるため腫瘍の局所制御率が向上します。
また炭素イオン線は従来のX線・γ線などの低LET(linear energy transfer)放射線とは異なり高LET放射線に分類されます。高LET放射線は飛程に沿って生じる単位長さあたりに電離する密度が高いため低LET放射線に比べ放射線損傷が回復しにくく、組織内酸素濃度や細胞周期の影響を受けにくいという特長があります。このため低LET放射線では効果が乏しかった組織型の腫瘍(骨肉腫、軟部肉腫など)に対しても有効性が期待できます。
重イオン線治療は、1975年に米国ローレンス・バークレー研究所で始まり、1992年までに主としてネオンイオン線を用い難治性腫瘍の治療が行われ、唾液腺、副鼻腔、骨軟部、胆道の腫瘍で有効性が示されています。わが国では1994年放射線医学総合研究所において炭素イオン線治療が開始され、2004年8月までに1954名に治療が行われ、2003年以後、眼球悪性黒色腫、頭頸部、頭蓋底、肺、骨軟部、前立腺、直腸がん術後局所再発に対して高度先進医療が実施されています。ドイツ国立重イオン研究所(GSI)でも1997年から炭素イオン線治療が行われており、今後、ドイツ(ハイデルベルク)、イタリア、オーストリアにおいても炭素イオン線治療が開始される予定です。
2.陽子線治療と炭素イオン線治療の選択
がんの治療は安全かつ有効に治療が行われる必要があります。当センターでは患者さんの腫瘍の種類、大きさ、状態に応じて最良と思われる粒子治療法を選択します。現時点でビームの選択ができるのは世界では唯一当センターだけです。
3.限局性腫瘍
対象臓器は決まっていませんが、原則として照射の対象となる病変と腸管との距離が2cm以上離れていること、孤立性の病変であることなどが必要です。ケースバイケースで治療の適応を決定します。詳細は当センターに電話(0791-58-0100)でお問い合わせください。
粒子線治療を希望される方へ
1.必要書類の入手
ホームページからダウンロードするか、県立成人病センター放射線医療室(TEL(078)929-1339(直) FAX(078)926-5401)に連絡し取り寄せてください。
2.主治医の先生に書類を渡し、FAXで放射線医療室に申し込んでください。
3.放射線医療室からの連絡をお待ちください。
なお粒子線医療センターでは直接新規の患者さんの診察は行っておりません。すべて県立成人病センター放射線医療室に受診していただき、治療の適応判断を行った後、粒子線医療センターの入院が決まります。
陽子線治療の現状
放射線科長 村 上 昌 雄
2003年4月から陽子線治療の一般診療が開始され、2005年2月で511名の患者さんに治療を行ってきました。
1.対象疾患
腫瘍の部位による内訳は下表のとおりです。
患者数は前立腺、肝、頭頸部、肺の順ですが、中でも頭頸部腫瘍では悪性黒色腫、腺様嚢胞癌、腺癌など放射線抵抗性と考えられる腫瘍が35名(76%)を占め、陽子線治療でも効果を示していることが特徴的です。
2.治療基準と治療成績
当センターでは各領域の専門家委員で構成される治療基準策定委員会で治療基準を作成し、それにしたがって適応を決定し治療を行っています。2003年4-12月に陽子線治療を行った180名のうち肝機能低下のため治療途中で中止した肝がんの1名を除いた179名の治療基準の適合性と再発状況について調べました。この期間は頭頸部癌65GyE(26回照射)、肺癌
80GyE(20回)、肝癌 76GyE(20回)、前立腺癌 74GyE(37回)、転移性肺・肝癌
56GyE(8回)の治療基準で治療を行っていました。240名の患者さんが希望され、適格148、不適格92名と判断されましたが、不適格と判定されても36名が治療方針検討会議にかけられ、臨床的に陽子線治療の適応はあると判断され35名が治療されています。この35名の治療基準外となった理由は、前立腺癌ではPSA>50ng/mlやホルモン療法抵抗性、肝癌では臨床的診断の問題や腫瘍径>8cm、肺癌や頭頸部癌では甲状腺癌合併でした。
これら179名の陽子線治療を受けた患者さんの1年後の再発状況を治療基準内144名と治療基準外35名に分けて検討した結果を以下の表に示します。
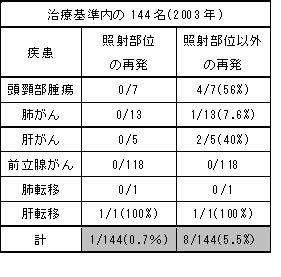 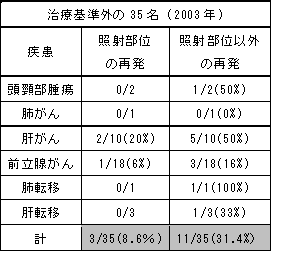
治療基準内144名のうち照射部位に再発を来た来たしたのは1名のみで、照射部位の再発率は0.7%と非常に良好な成績でした。一方、治療基準外の35名では照射部位以外の再発が3割を超えましたが、照射部位は8%台と低く抑えられていることがわかります。このことから陽子線治療は局所の腫瘍制御に有効で、たとえ治療基準外の患者さんであっても、局所病変を抑えることが臨床的に有用であろう判断された場合には、積極的に適用する価値があると思われます。
保守ネットワークの開設について
医療部放射線科 主任放射線技師
須 賀 大 作
かつて、機器と危機の管理を行う上で人のネットワークが重要であることを報告した。「三人寄れば文殊の知恵」ということで、放射線技師、物理技師、加速器技術者の三者で、治療効率向上の取り組みと機器管理を実施してきた。効率化では、コース切替え時間の短縮化や電磁石初期化なし運用など多くの成果を出した。機器の障害管理では15年度より、障害レベルを4段階に分類し記録することを開始した。15年4月から17年2月までの総障害件数は590件(表1)となった。1日1件以上の障害が起きていることになるが、装置部品数10万点から考えると、この件数が多いのか少ないのかを判断することは容易ではない。
障害分類 |
加速器系 |
照射系 |
障害1:治療不能 |
2 |
0 |
障害2:治療遅延 |
85 |
85 |
障害3:治療制限 |
51 |
10 |
障害4:治療可能 |
155 |
202 |
障害が起きると、復旧までの経過と作業内容を記録することとした。作業要領書、報告書、技術連絡書、障害管理表など多くの文書が発生した。ここまでくると、人のネットワークだけでは動きが悪くなってきた。
障害は大きなマイナス因子ではあるが、それを経験することで判断力と適応力が磨かれる。何よりエンジニアの技術力を高め、FTA(fault
tree analysis;故障の木解析)と呼ばれる障害の内容から原因を特定する手段が確立される。例えば、ランプがつかない場合、【1】ランプに欠陥がある。【2】電圧がかからない。の2点が考えられる。【1】の場合はさらに、フィラメント断線かソケット接触不良をチェックする。このように現象から原因を特定していく手法を確立させておくことで、正確かつ迅速な復旧が図れる。粒子線治療装置では、このFTAを充実させることが急務と考えられる。FTAは、装置ダウンタイムの減少と障害予防を図る上で重要なデータとなる。これらは障害によって得られるプラスの因子と考えることができる。FTAを構築するためには、データを集め、整理して解析することが重要なことは言うまでもない。幸いなことに(?)障害のデータは十分に蓄積されている。しかし、整理、解析となると紙資料と記憶だけでは限界を生じてしまう。これが「保守ネットワーク」誕生の背景である。上記の三者(ユーザー)と装置メーカーとをオンラインで結び、情報と保守管理データベースを共有化することを実現させた。
「保守ネットワーク」の運用目的は、【1】品質向上活動(加速器系、照射系、治療計画系)【2】保全活動(予備品管理、保守記録管理)【3】定期点検(点検記録、放射線安全管理)【4】情報の交換(インターネット回線による装置ログの送信、解析結果の受信等)である。相互の通信を担うネットワークのドメイン名は「ham-progress」とした。hamは、h(兵庫県スタッフ)とa(加速器技術者)m(三菱)を示し、粒子線治療の進歩、品質の向上を目的として連携する意味を込めた。
ハムネット(ham-net)と称する保守ネットワークは、平成16年9月より本格稼働を開始した。運用目的に従って分類された記憶装置(サーバー)に資料が蓄積されていく。必要に応じて資料を検索し、その内容を活用することができる。平成15年9月から17ヶ月間治療中止をさせずにきたが、加速器電源異常により連続記録が途切れた。前回は約2日の装置停止となったが、今回は11時間で復旧させることができた。機器の手配、原因特定、周辺機器への影響確認、復旧までの手順など、過去履歴を参照しFTAに従って対応した成果である。
保守ネットは装置の保守管理だけを目的に構築したものではない。人のネットワークを支援する道具として位置づけている。この装置には、実に多くの人が関わっており、その知識と経験を集約するのが保守ネットの役割である。したがって、蓄積されたデータを活用しなければ意味がない。例えば、治療の効率化を図るための課題を保守ネット上に置くと、様々な視点からの意見を集約することが可能である。意見をまとめるために、保守ネット上の多くの資料を参考にすることも可能である。
保守ネットが「三人寄れば文殊の知恵」をさらに進化させ、「文殊菩薩が三人寄れば」の知恵を生み出す道具となり、装置の安全性と安定稼働、治療効率の向上に大きな力を発揮することを期待したい。
医療事故防止への取り組み
看護科安全委員会 委員長 戎谷 明日香
医療事故防止への取り組み
H15年4月〜H16年12月までの経過から
看護科安全委員会 委員長 戎谷明日香
近年医療事故への関心が高まるなか、粒子線医療センターでは一般診療開始後H15年度250名、H16年度(12月まで)204名の方が医療事故を起こすことなく、治療を終えられました。
医療事故が起きないように、当センターでは電子カルテなどによる情報の共有化、エラー防止システムの整備、スタッフの安全への意識維持向上に努めています。また粒子線治療は切らずに治す癌治療で、侵襲性が低く、対象となる患者さんは自立された方がほとんどです。このことからも粒子線治療は従来の治療法より医療事故の発生頻度も少ない治療といえるのではないかと考えています。
しかし、1件の重大事故の影には膨大な数の小さなエラーが起こっているといわれていますように、その危険性は日常の中に潜んでいます。これらの「ヒヤリ」としたが事故に至らずにすんだ、「ハット」して事前にミスに気がついた等の状況を「ヒヤリハット」事例と呼んでいます。私たちは、「ヒヤリハット」事例をうやむやにせず、病院全体で取り上げ検討することで重大な事故を予防することに取り組んでいます。
◆◇H15年4月〜H16年12月までの集計結果◇◆
ヒヤリハット報告件数はH16年度がH15年度より増加しています。
これはヒヤリハット発生数が増加したというより、事故防止の職員意識が向上し医師・技師・事務からの報告件数が増えた結果と考えられます。
当センターで発生するヒヤリハット内容のうち頻度の高い上位3傑は与薬、治療・処置、転倒転落でした。この報告を元に、実際に改善策の一例として以下のような対策を取り入れました。
1)(与薬)外泊時の薬の渡し忘れ防止策として外泊時に声掛けチェック体制の徹底
2)(転倒転落)患者の状態(転倒転落の危険性)を入院時に判断しカルテに記載する。
3)(全体)入院患者の同姓同名、類似氏名をチェックし、イントラネットの掲示板に「類似氏名に御注意ください」を掲示し、全職員に注意を促す。
4)(全体)患者の取り違えを防止する目的で、電子カルテ上の3箇所(患者情報、病歴統計、治療カルテ)に患者顔写真を載せ随時確認可能にする。
5)(全体)検査や治療開始時には患者さんの氏名や注意事項・検査内容など確認の徹底をさらに強化。
これらの中で、件数が顕著に減少し効果の高かったと評価されるものとして転倒転落危険性判断シート導入があります。一般診療開始後まもなくのH15年4-5月のうちに5件の転倒がありました。幸い軽い打撲程度ですみましたが、スタッフの中に、『元気な患者さんが多いし、めったに起こることじゃないのでは』という思い込みがあったのではないかと話し合いました。そこで、転倒転落の事故の危険性を予測するための判断シート(事故が起きやすい要因がないかを知るための問診表)を導入しました。年齢・眠剤の服用・活動性・転倒歴などの情報を入院と同時にお聞かせ頂きながら相談することで、個別性にあわせた転倒予防法を共に考えることができ、職員・患者さんとも危機意識の向上と注意を促すことができました。今後は、よりセンターの特性にあったものに改良し患者さんの協力をあおぎながら安全性を維持し、安心して治療に望めるように更に努力していきたいと思います。
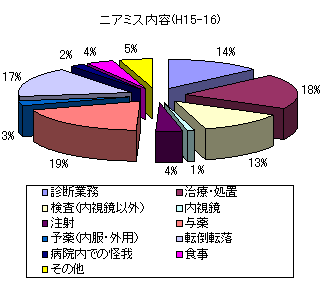
セカンド・オピニオンの実施について
セカンド・オピニオンは、病気の診断や治療法などについて患者さん自身が納得して治療を受けるために、主治医以外の専門医に意見を求めるものです。
当センターでは、患者の自己決定権を尊重し、患者の視点に立った医療を提供する一環として、平成17年4月からセカンド・オピニオンを実施します。
□対 象 者 主治医からの紹介状を提出できる患者又は家族
(家族の場合は患者本人の承諾書が必要)
□実 施 日 毎週金曜日(予約制)
□実施方法 専門医による面談(30分程度)
□料 金 保険が適用されず自費となります。
(料金は提供内容により異なり、例えばMRI画像による場合で12,900円)
□申込方法 予約制ですので当センター総務課まで電話でお申し込み下さい。
第4回病院運営懇談会を開催
病院運営に当って、県民の多様な意見を求め、県民の医療ニーズを的確に反映させるために、第4回病院運営懇談会が平成17年3月15日に開催されました。
主な内容
○ 保険適応について
○ 粒子線治療の受診方法について
○ 粒子線治療の副作用について
○ セカンド・オピニオンについて
陽子線治療にかかる高度先進医療の承認について
平成16年7月28日付で厚生労働大臣の承認を得て、平成16年8月1日より高度 先進医療として保険診療を開始いたしております。
※承認された高度先進医療の保険上の取扱いは、陽子線治療料(2,883,000円)については全額自己負担となりますが、入院・検査料等については、健康保険が適用されます。
二胡演奏会開催〜「花の季節に向かって」〜
二胡をご存知ですか?二胡(日本では「胡弓」とも呼ばれるが、日本の胡弓が三弦と四弦に対し、二胡は二弦)は1300年以上の歴史を持つ、中国を代表する弦楽器の一つで、その音色はゆたかで優しく、悲しい場面によく似合い、東洋のバイオリンとも呼ばれています。
当センターではこれまでもロビーを活用し、ピアノやジャズコンサートを開催してきましたが、今回は日本各地で演奏会に出演、また日中友好文化交流の架け橋としてご活躍中の二胡奏者王秀華先生のご厚意により、二胡演奏会を開催いただきました。
当日は患者さんや職員関係者約70人が集まる中、約1時間にわたって「川の流れのように」や「世界で一つだけの花」、「夜来香」などの演奏や患者さんと“共奏”もいただき、なごやかな雰囲気の中、二胡のやさしい音色にこころ癒される春のひとときを過ごすことができました。

|

