���Ɍ������q����ÃZ���^�[
�j���[�X���^�[No.24
April 2007
CONTENTS
�����@���q����ÃZ���^�[�̃C�`�S��
�����@���q�����Â̌�����
�����@�g���Ԃ��h�i���C�̎���j
�����@���q�����Ñ��u�@���̈���I�E�����I�^�]
�����@���ҁE��Î҂̃R�~���j�P�[�V����
�����@��܉Ȃ̋Ɩ��ɂ��ā`���@���̎��Q��`�F�b�N�ɂ��ā`
�����@�Ɖu�͂��グ��
�����@���q����Ãg�s�b�N�X
���q����ÃZ���^�[�̃C�`�S��
���Ɍ������q����ÃZ���^�[ �@���@�H��@�Ǖv
�@2003�N��ʐf�Â��J�n���܂������A10���̕��i����Ȃ鋐��ȑ��u�ŁA�N�Ԃ�ʂ��Ă̈�Â����S�ɁA�����ɐi�߂邽�߁A���̔N�̔N���̈��A�ŏ��߂āA�N�ԖڕW�̃C�`�S���i�ꌾ�A�L�[���[�h�j���f���܂����B�u�R���{���[�V�����v�ł��B��ÃX�^�b�t�A���u�X�^�b�t�A�����X�^�b�t�A���҂���A�Ȃ�тɑ��u���[�J�[���A�Ƃɂ�����ۂƂȂ�撣��Ȃ���A�ƂĂ����̗��q�����ÂƂ������u�ˑ��^�̈�ẤA����Ă����Ȃ��ƍl��������ł��B���̔N�̂T���ɂ́A���ɂ�鑕�u���̉ߓd���ŁA�ߌ�̎��Ò��ɑ��u���~�܂�܂����B�����Ƀ��[�J�[�̋Z�p�҂����āA���u�̃`�F�b�N�����A��x�����u���ċN�����A�䖝���Ē����ԑ҂��Ă������������҂���̎��Â��ĊJ�ł����̂́A���[�J�[�A��ÃX�^�b�t�A���҂���̃R���{���[�V�����̂������ł����B
�@2004�N�̃C�`�S���́u�y�������Áv�ŁA���Â��銳�҂��y�������Â��ł���悤�Ȋ�����i�߂܂����B�ϋɓI�ɃS���t�A�e�j�X�A�n�C�L���O�Ȃǂ����Ê��Ԓ��ɂ��邱�Ƃ�i�߁A���Â����퐶���Ŋy�����ł��邱�Ƃ�ڕW�ɂ��܂����B�ŋ߂ł́A���Z���^�[�̐f�ÃJ�[�h�ŁA�ߕӂ̃S���t��ŃS���t���ł���悤�ŁA�S���t��̋��͂ɂ���ϊ��ӂ��Ă��܂��B�܂��A�Q�N�O�ɂł����A�אڂ���̈�ق̗��p������銳�҂������A���Ê��Ԓ��ɃV�F�[�b�v�A�b�v�������������Ă܂���܂����B
�@2005�N�́u�i���v�ŁA���u��A�f�Öʂł̉��P��i�߂܂����B���ː��Z�t�A�����H�w�n�X�^�b�t�ƃ��[�J�[�̋�����Ƃł̕ێ�Ǘ��f�[�^�x�[�X�̍\�z�́A�Z�p�Ȓ��𒆐S�Ƃ���2003�N����n�܂��Ă����̂ł����A���u��i�������邽�߂ɁA���̉�͂�i�߂܂����B2006�N�Q���̑��u�ێ�̂��߂̂P�J���Ԃ̋x�~��A���u�́A�^�p�ʂő傫���ς��܂����B���̂X������[���̂T
���̋Ζ����ԑтŁA�P��30�l�̎��Â�����̂�����t�������̂ł����A�ێ�Ǘ����I�����Ă���̑��u�̍ĉғ���ɂ́A60�l��]�T�������Ăł���悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�P�N�ɂP��A�R-�S�T�̕ێ�x�~���Ԃ��K�v�������̂��A�P���ɂP��A�S-�T����ێ�_�����Ƃ��邱�ƂŁA�N�Ԃ�ʂ��Ă̑��u�ғ����������܂����B���̊ԁA���[�J�[�́A���Ɍ��̎w���̉��ŁA���_�̓����\�������Ă���A����̌㔭�{�݂ł̑��u�ɂ͂��̐��ʂ���������邱�ƂɂȂ�܂��B
�@2006�N�́A�u�n�b�s�[�Ȉ�Áv�ł��B��Î��̂�f�ÖʂŊ��҂���ƈ�Ñ����Η����邱�Ƃ��A�}�X�R�~�ő��������A��Â����邱�Ƃ��A���҂���ɂƂ��Ă���ÃX�^�b�t�ɂƂ��Ă��A���ɕs�K�Ȏ��オ�K��n�߂����Ƃ���������A���Ƃ��݂�Ȃ��n�b�s�[�ɂȂ��Â�ڕW�Ƃ�������������ł��B����Ȉ�Ë@�ւł��铖�Z���^�[�ł́A���Ì�̌o�߂����Ƃ��Đ����������Ƃ��厖�ŁA�܂��Ĕ����ȂǂɁA���₩�ɃA�h�o�C�X�ł���̐�����邱�Ƃ��A���҂���ƃZ���^�[�ɂƂ��Ẵn�b�s�[�Ȉ�Â̌��_�ɂȂ�ƍl���܂����B�����ŁA���҂���ɂƂ��đ厖�Ȍo�ߊώ@��g�D�Ƃ��Ăǂ̂悤�ɂ��Ă��������l���A��ÃX�^�b�t�Ǝ����X�^�b�t�ɁA���炵���a�f�A�g�����Ă��鈤�m���̃g���^�L�O�a�@�̌��w�����Ă��炢�A���̌��ʂƂ��āA�a�@�Ƃ��Ă̑g�D�I�Ȍo�ߊώ@������̐����ł��n�߂Ă��܂��B�܂��A���҂���́A��t�ɑ��Ĕ��Ɏア����̂��߁A�P�P�̐f�@�ł́A�\���Ȏv���������Ȃ����������̂ł����A���l�W�܂�Έ�t�ɑ��Ă����\�悭�����̎v����`�����邱�Ƃ�����܂����̂ŁA������Ō�t�̐i�s�̂��ƂŁA�s����ł����A���҂���Ɖ@���̍��b����n�߂Ă܂��B�����ł́A�P�P�̐f�@�ł͕����Ȃ��A���҂���̔Y�݂�A����ɑ���v���Ⴂ�Ȃǂ����Ƃ��ł��A�f�Âɂ��ǂ��t�B�[�h�o�b�N�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
�@���N2007�N�́A�u�j���[�R���{���[�V�����v�ł��B��ʐf�ÊJ�n��T�N�ڂŁA1300�����鎡�Â����Ă��܂������A���낻��f�ÂɂȂꂷ���鎞���ƍl���A2003�N�̌��_�ɖ߂�A�Q��ڂ̃R���{���[�V�������A�u�j���[�R���{���[�V�����v�Ƃ��āA�X�^�b�t�ɂ��肢���܂����B��N���̌o�ߊώ@���̑g�D���ɂ��A���҂���̌o�߂̔c�����i�݂����܂����̂ŁA��ÃX�^�b�t�̃j���[�R���{���[�V�����Ƃ��āA���܂ł̎��Ê��҂���̌o�߂�m��A����̎��Ẩ��P�E�i�����A��Õ����𒆐S�Ɏn�߂Ă��܂��B100�l�ȏ�̕����Ȃ��Ȃ��Ă���A��ÃX�^�b�t�ɂƂ��Ă��炢�d���ł����A�����ʼnߋ��ł̎��Ì��ʂ��w�сA�����̎��ÂɌ��ѕt���悤�Ƃ����l���ł��B�ŋ߂ł́A���q�����Â����ꂩ�珉�߂�{�݂���̌��C�����n�߂Ă���A��������������Ă̊e�{�݊Ԃł̃j���[�R���{���[�V�����̎n�܂�ƍl���Ă��܂��B�܂��A���Ìv��́A�]���A��t���S�Ă���Ă��܂������A�č����ɁA��t�̂��镔���A�i���Ǘ��m�i�č��ł̈�w�����m�j�̂��镔���ƁA���Ìv��ł̃j���[�R���{���[�V������i�߂܂��B���̂��߂Ɏ��Ìv�惁�[�J�[�Ƃ��b��������ʂ��ăj���[�R���{���[�V������i�߂܂��B
������@����@���Y
�P�D���Ê��Ґ��ƑΏێ���
�@2001�N�̎����J�n����2007�N�܂Ōv1478���̊��҂���Ɏ��Â��s���Ă��܂����B���Ê��Ґ��̐��ڂ����}�P�Ɏ����܂��B���߂̂Q�N�Ԃ͎����̂��ߎ��Ê��Ґ��͐�������Ă��܂������A2003�N�Ȍ�A�N�X���Ê��Ґ��͑������Ă��荡�N�x��514���ł��B
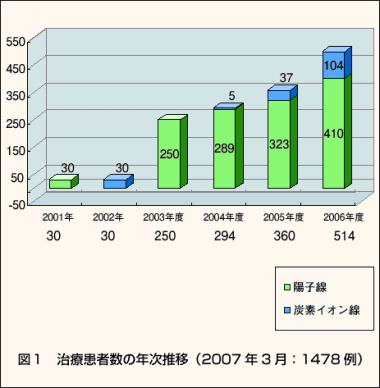
�@���ÑΏۑ���͑O���B��701���i47���j�ōł������A�ȉ��A����228���i15���j�A�̑�208���i14���j�A�x147���i10���j�̏��ł��B�O���B����͗z�q�����Â����Ŏ��Â��s���Ă���A����̈�̎�ᇂ̑����͒Y�f�C�I�������Â��s���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��i�}�Q�j�B
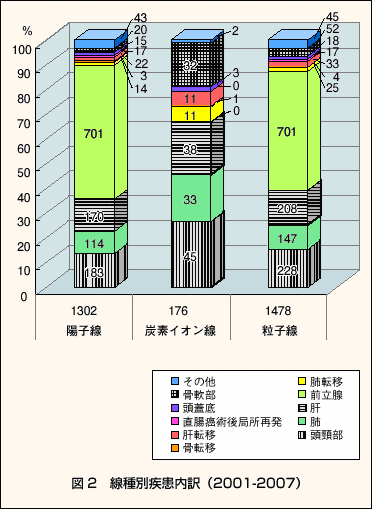
�@�N���ʂɎ����̊���������ƁA�O���B����̊������������A�̑�����⓪��ᇂ̊����������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��i�}�R�j�B
�܂��A��������p��Ĕ���]�ڂ���ȂǁA�V���ȑΏێ����̊��҂���������Ă��Ă��܂��B
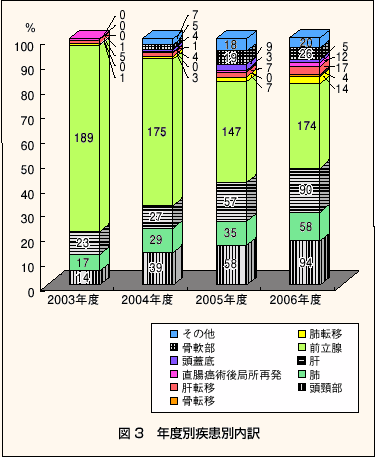
�Q�D�Љ�s���{����ʃx�X�g10�ƏЉ�a�@��ʃx�X�g�T
�@��ʐf�Â��n�܂��Ă���1418���̊��҂���Ɏ��Â��s���܂������A��Ë@�ւ�412�{�݂���Љ�������Ă��܂��B��Ë@�ւ̏��ݒn���猩��ƁA����717���Ƒ��286���������ł��B�ȉ��A���m47���A���s44���A�L��29���A����29���A�ޗ�23���A����20���A����20���A���R18���Ƒ命���͐����{�̈�Ë@�ւ���Љ��Ă��܂��B���\�P�͏Љ�̑���������Ë@�֏�ʃx�X�g�T��S�́A�����ʂɎ����܂����B
| �\�P �@�Љ�s���{����ʃx�X�g10�ƏЉ�a�@��ʃx�X�g�T |
|
|
�S��i�l�j |
1418 |
���i�l�j |
203 |
�x���i�l�j |
141 |
�̊��i�l�j |
199 |
�O���B���i�l�j |
683 |
|
| 1�� |
���ɐ��l�a�Z |
94 |
���ɐ��l�a�Z |
15 |
���ɐ��l�a�Z |
17 |
���Ύs���s�� |
43 |
���ɐ��l�a�Z |
37 |
| 2�� |
�_�ˑ� |
86 |
�_�ˑ� |
14 |
��㐬�l�a�Z |
10 |
�_�ˑ� |
16 |
�P�H�ԏ\�� |
30 |
| 3�� |
�P�H�ԏ\�� |
45 |
�P�H�ԏ\�� |
8 |
�����R |
5 |
���ɐ��l�a�Z |
10 |
�_�ˑ� |
28 |
| 4�� |
���Ύs���s�� |
45 |
���� |
8 |
�_�ˑ� |
5 |
�ϐ���Ɍ� |
7 |
�V���c�L�� |
24 |
| 5�� |
��㐬�l�a�Z |
36 |
��㐬�l�a�Z |
6 |
��㑍����ÃZ |
4 |
�ԕ�s�� |
6 |
����A��� |
22 |
|
|
���5 ���̌v |
306 |
|
51 |
|
41 |
|
82 |
|
141 |
|
|
|
��߂銄�� |
22% |
|
25% |
|
29% |
|
41% |
|
21% |
|
|
�R�D��Ȏ����̍ŋ߂̎��Ð���
�@��Ȏ����̂R�N�������A�R�N�Ǐ����䗦�i����ᇁA�x����A�̂���j�A�R�NPSA���䗦�i�O���B����j��\�Q�ɂ܂Ƃ߂��B����ҁA�����Ì�̍Ĕ���A���x�x�C��A�̍d�ςȂǂ̎�p�s�\�ȏǗ���܂�ł��܂��B�ώ@���Ԃ��[���ł͂Ȃ��̂ƁA��͂��s�\���ł��̂ŁA����̌����Ő��l�͕ω����邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ��ł��B��ʂɓ���ᇂ͎�p�s�\�Ȏ����A��p��̍Ĕ���Ȃǂ��܂ނ��߁A�S�̂̐��т͑�������舫���Ȃ��Ă��܂��B�ڍׂȌ����͐�ɏ��邪�A�����_�ŗ��q�����Â̊��҂���鐬�ʂ������Ă���ƕ]�����Ă��܂��B
| ���� |
�Ώ� |
�ᐔ |
3�N�������i%�j |
3�N�Ǐ����䗦�i%�j
3�NPSA ���䗦�i%�j |
| ����ᇑS�� |
2001-07.1 |
208�� |
42 |
66�i�Ǐ����䗦�j |
| �x����I�� |
2001-07.1 |
111�� |
78 |
81�i�Ǐ����䗦�j |
| �̂���S�� |
2001-07.1 |
186�� |
61 |
84�i�Ǐ����䗦�j |
| �O���B����A,B,C �Q |
2003-04.12 |
291�� |
98 |
92�iPSA ���䗦�j |
�g���Ԃ��h�i���C�̎���j
��Õ��@���ː��Z�p�Ȓ��@�{��@���
�@���o�̗p��ɁA�����b�ɂȂ����Z��q���甒���������邱�Ƃ��u���Ԃ��v�Ƃ������킵������܂��B���́u���Ԃ��v�Ƃ������t�́A�����b�ɂȂ����������ł��ꂾ���̐��ʂ��o�����Ƃ��ł��܂����Ƃ����Ⴆ�Ƃ��čL���g���Ă��܂��B
�@19�N�S���A���Ɍ��̗��q�����Î{�ݗ����グ�Ɋւ���Ă���10�N�ڂ��}���܂��B���̂P�N�ځA���Ɍ����ɐݒu����Ă����������ɁA����܂ł̔��߂���X�[�c�ɕς��ď��o������������̂��Ƃ̂悤�Ɏv���o���܂��B�ْ��Ɩ��m�Ȃ���̂ւ̕s�����ŁA���炢���ɗ��Ă��܂����Ƃ����v���ł����ς��ł����B�����ɗ��������܂��Ȃ��A���q�����Â��s���Ē��肵�Ă�����������Z���^�[���a�@�A���ː���w�����������i�ȉ��A���㌤�j���C�Ɍ������܂����B���C��ł́A��t�A�Z�t�A���u�Ɋւ�镨���̕��X�ɉ������}������Ă��炢�܂����B�ْ���s���̂Ȃ��Ŏ��D�����́A���Ԃ��o���Ă����������ɑN�₩�ȋL���Ƃ��Ďc���Ă܂��B
�قڂP�N�ɂ���Ԍ��C�̐��ʂ𗊂�ɁA���̌�[�����Ă����X�^�b�t�Ƌ��Ɏ{�݂̗����グ���s���܂����B���O���čs��ꂽ�����t�𒆐S�Ƃ��鐶��������d�q�J���e�V�X�e���̗����グ�A���Ìv�摕�u��f�f�@��̒����ȂǑ����̐������ڂ���l��l���ӔC�������Ď��g�݂܂����B
�@�ߍ��A���̗����グ�������悭�v���o���܂��B�Ȃ��Ȃ�A�X�N�O�̎�������X���邱�Ƃ��ł��邩��ł��B18 �N�W���A����21�N�x�z�q�����Î{�݂̊J�݂�\�肵�Ă��镟�䌧���a�@����̌��C������܂����B������10���A����20�N�ɓ������z�q�����Î{�݂̊J�݂�\�肵�Ă��镟�����̑����쓌�k�a�@����̌��C������܂����B�܂��ɁA�ނ�̎p�́A��������Z���^�[���a�@����㌤�ł����b�ɂȂ�����X�̎p�Ȃ̂ł��B�ނ�́A���Ɍ��̗��q�����ÃV�X�e����ʂ��Ď��������̗����グ�Ă����{�݂̉������s���Ă��܂��B�����Ɍ������ۑ���������Ă������ƂŁA�����グ��{�݂̃C���[�W�𗧑̓I�ɂ��Ă���̂ł��B
�@���C�������ɂ�����A�K���ɂ��A����܂Ńv���W�F�N�g�Ƃ��čs���Ă����u�v�Z�@���x���v�u�ێ�l�b�g���[�N�v�u�ێ番�U�Ǘ��v���������I���ĉғ����J�n���܂����B�@�v�Z�@���x���́A117���ɂ���Ԍ������Ă��V�X�e���Ƃ��Ď������������̂ŁA���S���Ɛ��x�Ȃ����ƂȂ����I�Ȏ��ԒZ�k�����������܂����B�A�ێ�l�b�g���[�N�́A���u�Ɋւ�������f�[�^�x�[�X�Ƃ��č\�z�������̂ŁA�Z�p�X�^�b�t�A���u�^�]�Z�p�ҁA���[�J�[�̎O�҂��������L����V�X�e���ł��B�����ɒ~�ς��ꂽ�f�[�^�����݂Ɍ���������A�{�����邱�Ƃő��u�g���u�����̕����܂ł̎��ԒZ�k�ɖ𗧂ĂĂ��܂��B�����������W��ł���ێ�l�b�g���[�N�́A����x���̃c�[���Ƃ��Ċ��p���邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�B���Â�ʔN�s���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���18�N�S�����ێ番�U�Ǘ��̉^�p���J�n���܂����B�ێ�U���邱�Ƃɂ���āA���Â����ł͂Ȃ����C���ʔN����邱�Ƃ��ł���̂͂悢�Ӗ��őz��O�ł����B���Ãz�[���Ɍ��C�̋Z�t�Љ���f�����Ă��܂��B���҂���{�݂̊J�ݎ�����ꏊ�ɂ��Ď�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��悤�ŁA���������̎{�݂̃p���t���b�g��u���悤�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B���̕����������Ă����̂��A�ƂĂ��������悤�ŁA���̋C�������{�ݗ����グ�̌����͂ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B
�@�{�݂𗧂��グ�Ă����ߒ��ł́A�l�X�ȉۑ������邱�ƂɂȂ�܂��B��X�́A���̎��X�Ƀv���W�F�N�g������ă`�[���͂ʼn������͂����Ă��܂����B�����āA�v���W�F�N�g�̖ړI�m�ɂ��邽�߃l�[�~���O���s���܂����B�z�q���ƒY�f�C�I�����̐ؑւɂP���ԋ߂���v���������ɁA���Ƃ�30�����P���ł��肽���Ƃ��āu29���v���W�F�N�g�v���J�n���܂����B���݁A�ؑ֎��Ԃ�13���ɂ܂ŒZ�k����Ă��܂��B�ړI�m�Ɏ����l�[�~���O���s���ăv���W�F�N�g���J�n���邱�Ƃ͌��ʓI�ł����B�������A���̃l�[�~���O�Ɏl�ꔪ�ꂷ�邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��A���`�x�[�V���������߂錾�t��͍����Ă��钆�ŁA�f���炵�����t��������ɒ����܂����B����́u�N�̂��߂ɁA���̂��߂Ɂv�Ƃ������t�ŁA����Ȃ�A�u���҂���̂��߁A���Â̈��S�̂��߁v�ƖړI�m�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B�����āA���̖ړI�͒B�����ꊮ��������̂łȂ��A�p������Ă������̂ł��B���C�ŁA���������w�͂��K�v�Ȃ��Ƃ�`���邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B���C�����Ƃ��āA�{�݊Ԃ̘A�g�����܂�邱�Ƃ����������������Ƃł��B���悢�{�݂𗧂��グ�Ă��炤���߂ɁA�ł��邾���̎���ɂ��܂��ɋ��͂��Ă����܂��B����́A���ĉ�X�����C�����{�݂���w�p���ł���A���̂��Ƃ��A�܂��Ɂu���Ԃ��v�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
���q�����Ñ��u�@���̈���I�E�����I�^�]
���u�Ǘ��Ȓ��@�� ���j
�@���Ɍ����q�����Ñ��u�́A1999�N�̎����^�]�J�n�ȗ��A�����A��ʐf�Â̂��߂̉^�]�𑱂��A2007�N�P�����ŗv��29,000���Ԃ̉^�]���s���Ă����B���̉^�]���Ԃ̐��ڂ��A�����̏���d�͂̂R�����ړ����ςő�ւ��\���������̂��A2003�N�S����ʐf�ÊJ�n�ȗ��̌��ԐV�K���Ґ��Ƌ��ɉ��}�Ɏ����B�����^�]�A�������̉^�]�Ɋr�ׂĈ�ʎ��Î��́A���R�̎��Ȃ�����肵�Ă��邪�A�N�P��s��ꂽ��R
�T�Ԃ̒���_�������ɑΉ����ĉ^�]���Ԃ����Ґ�����������̂����Ď���B�������Ȃ���2006�N�t�̒茟�ȍ~�́A�茟�����P�Ƃɕ��U���{���邱�Ƃɂ��A�����肵�Đ��ڂ��Ă���B�茟���O�̏T���͈�ʏT��_�����s���A�r�[���Ē����^�]���͒茟�I�����̃r�[���m�F�^�]�Ƌ��ɓZ�߂čs�����Ƃɂ��A�^�]���Ԃ�����������ʂ����Ď���B�ߋ��̉^�]�̈��萫�A�Č����̎��т���A���ÏƎ˂̎��_�̂݃r�[���A���n�d����ʓd���ҋ@���̓I�t���邱�Ƃɂ��A����w�̏ȃG�l���M�[�����������B���̌���2006�N�x�͂���ȑO�Ɋr�ׂĊ��Ґ����������ɂ�������炸�A�^�]���ԁA����d�͂Ƃ��Ɍ����X���ɂ���B�܂����Ìv��̐��x���тɂ��A�������߂�O���B���҂̏Ǝ˃p�����[�^�[�͐V��������ȗ����ė��_�v�Z�l��p���邱�Ƃ��\�ƂȂ����B���ʍ�N10���ȗ��X�ɉ^�]���Ԃ������X����\���Ă���B�ȑO�͂P�N������̉^�]���Ԃ́A4100���Ԃ��Ă������A��N�ȗ����X�Ɍ����𑱂��A���݂�4000���Ԃ�����悤�ɂȂ��Ă���B����Ƃ����̃y�[�X���ێ����A����I�A�����I�ȑ��u�^�]�ɓw�߂����B
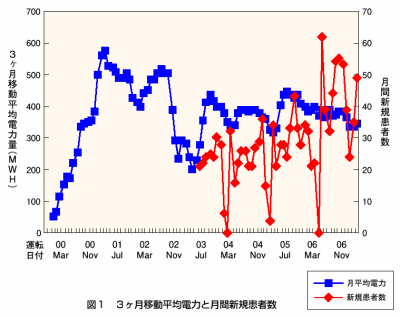
���ҁE��Î҂̃R�~���j�P�[�V����
�Ō�ȁ@����Ō���Ō�t�@���{�@����
�@�ߔN�A�g���鎡�Áh�܂��́A�����I�łȂ��Ă��g�a�C�Ƃ������Ă����鎡�Áh�����B���Ă������Ƃɂ��A���҂��g���ǂ̂悤�ɕa�C�Ƃ������Ă��������l���A�����ɂ��������Ö@��I���悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@���̂悤�Ȓ��A���q�����Â���ꂽ���҂���̒�����g��Î҂Ƃ����ƑΘb���������h�g���̊��҂��ǂ̂悤�ɕa�C���~�ߎ��Â��撣���Ă���̂��b�������h�g���������ɂƂ��Đ�y���҂��搶�ł���h�g�����̑̌��𑼂̊��҂���ɖ𗧂Ă����h�Ƃ����ӌ��𑽂����ɂ���悤�ɂȂ��Ă܂���܂����B�����ʼnƑ����܂߂�15
���O��̊��҂���Ɖ@���A�Ō�Ȓ��A����Ō���Ō�t�炪���Ȃ��A���R�ɘb���鍧�b������ɐ���J�Â��邱�Ƃɂ��܂����B���̒��ŁA����Ɛf�f���ꂽ���̃V���b�N�A�撣�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����Ƒ��̌��t�A���҂��m�̗�܂������A���Ì�̉߂������͂ǂ�������悢�̂��ȂǁA���܂��܂Ȋ��҂���̐S�̒�����ɍ��������̌���b���Ă��������܂����B���b��I����̊��z�ɂ́A�ق��̊��҂���̕a�C�Ƃ̂��������Ȃǘb�������Ă悩�����Ƃ������z����������A���҂���ɂƂ��āu�����̌������l�v����̉����̎x���ɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B�܂��̌���l�ɘb�����ƁA����͂���Ɏ���������������̂ł���Ǝv���܂��B���̂悤�ȉ��ʂ��āA�܂����҂���̗~���̒��ɂ́A�̌������L�������C�����Ɠ����ɁA���������̊��҂���̖��ɗ��������Ƃ����~���������ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ������܂����B���̊��҂���̖��ɗ��̂ł���ƁA���G�Ȋ��҃J���e�V�X�e���ł̌o�ߊώ@�ɑ����̊��҂����͂��Ă��������Ă��邱�Ƃ�����f���܂��B
�@�����Ĉ�Î҂ɂƂ��Ă����҂�������̌��́A���҂���������������A��Î҂̖����͉������l����悢�@��ƂȂ��Ă��܂��B
�����Âɂ����ăO���[�v���炪����ɂ��������w�i�ɂ́A�s���̕a�̃C���[�W���������݂��̋����⓬�a�̕��@�����L���邱�Ƃ�����������Ƃ��������܂��B�u���҂��m���p�[�g�i�[�V�b�v�����v�Ƃ������Ƃ���j�I�ɒ��ׂĂ݂�ƁA�A�����J�œ��K�����҂̓��[�؏��p��̐��_�I�Ȗ������̂��߂ɍ��ꂽ����܂��܂Ȋ��҂��m�̎x���v���O�����̃��f���ƂȂ��Ă��܂��B����ɂ���ɂȂ����Ƃ������Ƃ��A�����J�ł͎Љ�I�ȉ����ł���Ƃ������オ����A1950�N��ɂ͂����҃N���u���A���҂��Љ�I�������邱�Ƃɗ�����������Ƃ��Ĕ��W���Ă����悤�ł��B���݁A����͂R�l�ɂP�l��������g�߂ȕa�C�ł���A����ƕt�������Ȃ���Љ�A����Ă���������������A���҂���̃C���[�W���ω������҂��m�̃p�[�g�i�[�V�b�v�̌`���ω����Ă��Ă��܂��B���ғ��m�̑��݉����̍l���́A�������g���݂߂���A���݂��ɉe����^�������č�����������Ă����Z�p�����������Ƃɉ��l��u�����悤�ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B
�@���q����ÃZ���^�[�ł̍��b��ł́A���ꂼ��̊��҂���̑̌��͉��l������̂ł���A�����ɂ���l�����̊����̌��������ł�������A������肷�邱�Ƃ����������Ȃ���A���҂��m����Î҂��p�[�g�i�[�V�b�v�������e����^�������Ȃ���𗬂����Ă���Ɗ肢�܂��B
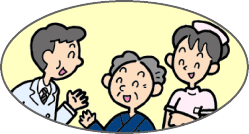
��܉Ȃ̋Ɩ��ɂ���
�`���@���̎��Q��`�F�b�N�ɂ��ā`
�@���҂���̑����́A���炩�̂���p����Ă���A����������ē��@���Ă����܂��B�]���͑S���I�ɂ݂āA�قƂ�ǂ̕a�@�ɂ����Ė�t�̐ϋɓI�Ȋ֗^�͂Ȃ���Ă��܂���ł������A���Q��Ɋ֘A������Î��̂������������Ƃ��A���҈��S�m�ۂ̈�Ƃ��Ė�t���֗^���闬��ƂȂ��Ă��Ă��܂��B
�@���@�ł́A��R�N�O�����t���S�Ă̎��Q����m�F���Ă��܂����A����́A���̋Ɩ��ɂ��ďЉ�����Ǝv���܂��B
�y�T�@�v�z
- ���҂���̓��@���ɁA�Ō�t�͊��҂���̎��Q����܉Ȃɓn���A��t��������`�F�b�N����B�i��ǂōw���������i�A�T�v�������g���܂ށj
- ��t�́A���Q����i��i���A����A���p���@�A�c���A���@�̗p��i�̗L���⑊���i�Ȃǁj���쐬���A��t�E�Ō�t�ɕ���B
- ��t�́A���p���p�����邩�ǂ��������肵�A�Ō�t�E��t�ɕ���B
- ��t�́A�����̏����J���e�ɓ��͂���ÃX�^�b�t�ŏ������L����B
- �K�v���ɂ́A����������Ë@�ւ⒲�܂�����ǂɓ��e���m�F����B
�y�����b�g�z
- ���@�ŐV���ɖ������ꂽ�ꍇ�A���Q��Ƃ̈��ݍ��킹��d�����Ė�������Ă��Ȃ������`�F�b�N�ł���B
- ���Q�Ȃ��Ȃ�A���@�̗p��i�ɐ�ւ�����ꍇ�A���^�ʂ╞�p���@���K�ł��邩�ǂ����`�F�b�N�ł���B�܂��A���҂���ɑ��A�]���g�p����Ă�������Ƃ̈Ⴂ��K�ɐ������邱�Ƃ��ł���B
- �g�p�ɒ��ӂ��K�v�Ȗ�܁i�Ⴆ�A�R������ᇖ�����ȗp�@�̈��i�Ȃǁj�ɂ��Ĉ�ÃX�^�b�t�ɕK�v�ȏ�����邱�Ƃ��ł���B
�@���@�ł͖�t���P���̂��߁A��t�s�ݎ��́A�Ō�t���u���Q��ꗗ�\�v���쐬���A�����ɖ�t���m�F���܂��B���̂悤�ɃX�^�b�t�Ԃ̘A�g�𖧂ɂ��A�Ö@�̊ϓ_��������S�E���S�Ȉ�Âɓw�߂Ă��܂��B
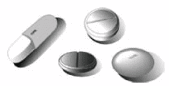
�Ɖu�͂��グ��
�h�{�m�@�����@����
�P�D�H���Ǝ��B���抪����
�@�ŋ߂ł́u�����v�Ȃǂ����s���Ă���悤�ɁA�����������̂�H�ׂ�̂��D���A�H�ו����̂���Ƃ������������A�H�ɂ��āA�u���������v�����ł͂Ȃ��A�{�₻�̓y�n�ł����H����Ă��Ȃ����������́A�_�C�G�b�g����e�Ȃǎ��v�͂܂��܂����܂��Ă��܂��B���@���̊��҂���ɂƂ��Ă��A�H���͂P�Ԃ̊y���݂Ƃ悭�����܂��B��Â̌���ł��A��t�ɂ�鎡�Â��ƕ���ŁA�H���Ö@���ƂĂ���Ȉʒu�Â��Ƃ���Ă��܂��B�ߔN�ł́A�h�{�����e���r��G���Ȃǂł킩��₷���Љ��Ă���A���^�{���b�N�V���h���[���Ȃǂ��n�߂Ƃ��āA��ʂ̕��X�̌��N��h�{�ɂ��Ă̊��S�́A�܂��܂����܂��Ă��܂��B����ŊԈ��������A�T�v�������g�Ȃǂ̕�����ʐێ�Ȃǂɂ���ĉh�{��Q���N���������������܂��B
�Q�D�K���ɂȂ�Ȃ��A�Ĕ������Ȃ����߂̐H���A���Â���
�@���Z���^�[�ɓ��@���̊��҂�����H����h�{�ɂ��Ă̋����������Ă�������������A�������������X�ւ̏��̏�Ƃ��āA�݂�Ȃ��W�܂�H���Ɍf����V�����ݒu���܂����B�܂��͕a�@�h�{�m����̏��B�����ĊŌ�Ȃ���̘A��������f��ӏ܉�̂��m�点�A����ɋ��H�Ǝ҂���̐H���ɂ��Ă̏Љ�ȂǂȂǁB�H����H���̏ꏊ�����ɂ����A�S���e�n���痈���Ă��銳�҂��m�̉�b�����܂��ꏊ�Ƃ��Ċ������Ă�����Ǝv���Ă��܂��B�y�������͋C�́A�Ɖu�͂����߂�ƂƂ��ɁA�a�C����̉������A�Ĕ��h�~�ɂ��q����܂��B���҂���̊e�����ւ̎�����t���Ă���A�ɂ��Ă�����o���Ă���܂��B�H���ł́A�f�������łȂ��A��ނ��x��ĐH�����������⋍�������߂����Ȃǂ̊�]���ȑO���炠��܂����̂ŁA�d�q�����W�̐ݒu�i�Q��j�����킹�čs���܂����B����ɂ���āA�H���̉��߂͂������A���H�̋��������߂ăJ�t�F�I��������������ꂽ��ƁA�����₩�ł͂���܂������̌��オ�ł������̂Ǝv���Ă��܂��B�H�����e�ɂ��ẮA�������݂��тȂǂ̖��t�����т�˗ނ̊�]�������A���݂͏T�P���ڕW�ɖ��t�����тƖ˗ނ����{���Ă���܂��B���t���ɂ��Ă��A�a�@�h�{�m�Ƌ��H�Ǝ҉h�{�m�����c�����{�Ƃ����`���Ƃ��Ă���A�H����ɂ��Ă��]�����A����ɐ�������悤�ȑ̐����Ƃ��Ă���܂��B
�R�D����̎��g��
�@��t��Ō�ȁA��܉ȂƘA�g����NST�i�h�{�T�|�[�g�`�[���j���������Ă����A���z���̎��Â�����Ă��銳�҂�����n�߂Ƃ���H����ۂ�ɂ������ւ̒�h�{��Ԃ̉���A���P�����Ă��������Ǝv���Ă��܂��B���̑��ɂ��A�S������W�܂���ցA���Ɍ��̋��y���������Ȃǂ̂���Ȃ郁�j���[�̏[����A���H�̕ĔѐH�A�p���H�̑I�����A�T�P����x�̎��肨���i���Ȃǂ��l���Ă���܂��B�܂��A�H���ȊO�ł��A�����K���̌������Ƃ��āu��������v�Ȃǂʼn^���K����g�ɂ�����悤�Ȋ����ȂǁA���@���Ӗ��̂�����̂Ɋ����Ă���������悤�A���P�𑱂��Ă��������Ǝv���܂��B
���q����Ãg�s�b�N�X
�n���� ����t����w���m�������^����܂����B
�@���Z���^�[�ɕ���18�N�R�����܂ōݐЂ���A���݁A����ɍ�������Z���^�[�����a�@�i�����s������z�n�T�|�P�|�P�j���ː��ȂɂāA�f�Â𑱂��Ă�����n�������搶���A���̂��ш�w���m���i�_�ˑ�w�j�����^����A�_�����č��̈�w�G���Ɍf�ڂ���邱�ƂƂȂ�܂����B
�@�搶�́A���Z���^�[�ݐE�����犳�҂���̎��ÂɑS�͂��X�����A���̌����̐��ʂ�����̎擾�ɂȂ��������̂ƃX�^�b�t�ꓯ���ł��܂��B
�G�����FInternational Journal of Radiation Oncology,Biology,Physics�i�č����ː���ᇊw��j
��@���FAcute morbidity of proton therapy for prostate cancer:the Hyogo Ion Beam
Medical Center experience
�i�O���B���ɑ���z�q�����Â̋}�����L�Q���ہF���Ɍ������q����ÃZ���^�[�ł̌o���j
���ҁE�������F�n�������A���㏹�Y�A�����j�A����čƁA���c�N�]�A�{�e���A���X�ؗǕ��A�����a�N�A�H��Ǖv
���@�e�F�z�q�����Â̋}���������L�Q���ۂ͏]����X ���O�Ǝ˂ŕ���Ă���p�x���͂邩�ɏ��Ȃ��A�z�q�����Â̓����ƍl������B
���{���ː���ᇊw��iJASTRO�j�̏��F��{�݂ɂȂ�܂����B
�@���q�����Â��s���{�݂́A���ݍ����ɂU���������Ȃ��A���q�����Â��s�����t��{�����Ă������Ƃ́A����A���q�����Ây�����Ă������߂ɂ��s���ł����A���̂��сA���Z���^�[�ł̋Ζ��N�����A���ː��Ȑ���Ƃ��Ă̊w��F�莑�i���擾���邽�߂̌o���N���Ƃ��ĒʎZ�ł��鏀�F��{�݂ɔF�肳��܂����̂ŁA���m�点���܂��B
�@������A���q�����Â��s���Ă݂����Ǝv����t���S�����猤�C�ɗ��Ă����悤�Ȑ�i���Â̎{�݂Ƃ��Ď��т�ς�ł����ƂƂ��ɁA��l�ł������̕������Âł���a�@���߂����Č��r�ɗ��ł܂���܂��B
|

