���Ɍ������q����ÃZ���^�[
�j���[�X���^�[No.28
June 2009
CONTENTS
�����@�n���ÂƍL����
�����@���Î��сi2009�N�R�������_�j�Ǝ��Ê�̉���
�����@���q����ÃZ���^�[�ɂ�����Ō�t�ԘA�g
�����@�쓌�k����z�q�����ÃZ���^�[�̊J�ݔ��N��U��Ԃ�
�����@���q����ÃZ���^�[�ɕ��C���ā`�l�Ƃ̂Ȃ���`
�����@�S�N�Ԃ�U��Ԃ��ā`�a�@�̐i���`
�����@���Î����̊g��ɑ������Ō�Ȃ̎��g��
�@�@�@�@�@�@
�����@��W��a�@�^�c���b�� �J��
�����@�Z�J���h�I�s�j�I�������̉���
�n���ÂƍL����
���Ɍ������q����ÃZ���^�[ �@�@���@�H�� �Ǖv
�P. �n����
�@���{�̈�ẤA�����̂ǂ��ɏZ��ł��Ă��A�����a�C�̎��Â����ꍇ�ɁA�����̈�Â����悤�ɍ\�z����Ă����B���E�̂ǂ̍������A���Ɍ������̗ǂ���ÃV�X�e���ł������B�����A�ŋ߂��̒n���Â����n�߂Ă���B�傫�Ȍ����́A��t�s���ł��邪�A���n�߂Ă��܂�����ÃV�X�e���́A�Ȃ��Ȃ����̂悤�ɂȂ�Ȃ��̂ł͂Ɗ뜜���������ł���B���āA���҂̑�����݂��n���ẤA�n��̕a�@�ɍs�����ƂŁA���Җ{�l�͂��܂�l���Ȃ��ł��A�ǂ���Â��鎖���\�ł������B�������A���������V�X�e�����A���n�߂Ă���n��ł́A�ȑO�̂悤�ȗǎ��Ȉ�Â����҂��Ă����̂ɁA���҂ɔ������ꍇ�A���҂͕s���������A�V�X�e������ł͂Ȃ��A�厡��̌��ʐӔC��₤���ƂƂȂ��Ă������߁A�撣���Ă����t���A�撣��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���̈��z���A����Ɉ�t�s���������炷���ʂƂȂ��Ă��Ă���B
�@��t�ȊO�̕��Ƙb�����ċC�������̂����A��Ƃ̋ΘJ�҂��e�n�ɓ]����ꍇ�A�n���ł���A�{�l�������P�g���C���A�����ւ̓]�ł���A�Ƒ������Ă����Ƃ��������ƁA�n���̈�t�s���́A��ÃV�X�e�������̖�肾���ł͂Ȃ��A���Ȃ�[���ł���B���Ȃ킿�A�������l���Ђ����Ă���A���̂��Ƃ͈�t�ɂƂ��Ă��������Ƃ������Ƃł���B
�Q�D���_�a�@
�@���҂���l�����ꍇ�A�����ȁA�Y�Ȃ⍂��҂Ɋւ���f�ÉȂ́A�n�斧���^�̈�Âł��邪�A�����K���a�ł��邪���z��a�����A�܂��A�����̐��a�@��ЊQ�E�~�}�̐��a�@�́A�L���n��̋��_�ɕK�v�Ȉ�Âł���B���������āA�L���n��ł̋��_�����K�v�ŁA�n���Õa�@�̈�t�����_�a�@���I�[�v���ɗ��p�ł���悤�Ȏd�g�݂����A�n���Õa�@�ɓ����l�Ȑݔ���ݒu���邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�Ɠ����ɁA��t���L���Ɋ���ł���d�g�݂��ł���B���{�̈�Â̌��_�́A�n��̌����������ߑ��������߂ɁA��Î��Y�����܂�ɂ����U�������������Ƃł���B���ː����Â̗̈�ł��A700�������ː����Ñ��u�������ɂ���A�����́A���Έ�t�Ŏ��Â�����Ă���B���U������߂ċ��_������A���̂悤�Ȃ��Ƃ͉����ł���\��������B
�R�D�L����
�@���q�����Â͍L���Âł���A���Z���^�[�́A�S�Ă̓s���{������̊��҂��������Ă���B2009�N�R�����ŁA2500�����鎡�Ð��ŁA��45�������Ɍ����ŁA���A���m�A���s�Ƌߌ��������Ă���A�L���Âł����Ă����b���Ă���������́A�{�݂ɋ߂��A�{�݂�m��@��̑����������ł���B�L���Â̓����́A���҂������Œ��ׁA��]���Ď��Â����Âł���B�n���Â̂悤�ɁA���҂��l���Ȃ��ł����̒n��ł̍őP�̈�Âɂ��ǂ蒅����Âł͂Ȃ��B�L���ẤA���炩�ɒn���ÂƂ̈Ⴂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Z���^�[���J�@�����́A���̎��Âł��\�ȑO���B����⑁���̔x���҂������A�n���Â̈�t�����̗������Ȃ��Ȃ������Ȃ������B�ŋ߂ł́A���̎��Âł͍���Ȋ��҂�40�����A���̎��ɂ��A�n���Â�S����t�����ɂ���������A�厡��̊��߂������Ă����ƍl���Ă���B
�S�D�O���[�o���^���
�@�C���h��^�C�Ȃǂōs���Ă��郁�f�B�J���c�[���Y���̂悤�ȁA�O���o�[���[�[�V�����ɉ�������Â��e���Ŏn�܂��Ă���B����́A�O���[�o���^��Âł���A���{����C�O�ֈڐA���ɍs���̂́A����ł���B���q�����Âł́A�C�O�ɏ\���Ȏ{�݂��Ȃ����Ƃ���A���Z���^�[�ł����܂łɐ��l�̊C�O�̊��҂�������Â��Ă����B�L���Âł��闱�q�����ẤA���̂܂܂ł��O���[�o���^��ÂƂ��Ă���Ă��������ł���B
�@���ƌ�̊O�Ȉ�u�]�����������Ă��邪�A�n�C���X�N�E���[���^�[���ł��邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A�ی��f�Â̘g�ł݂̂����ł��Ȃ�������Ⴂ��t�̃��`�x�[�V�����ɂ��Ȃ�e�����Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl����B�O�Ȉ����Ȉオ�K���Ɉ�Â����邽�߂̈�Ƃ��āA�O���[�o���^��Â������̓��{�̈�ÂƂ��čl���Ă݂Ă͂ǂ����낤���B
�T�D�����̓W�]
�@�ʏ�̂��Â͋��_�a�@�ōs���A���q�����ÂȂǂ̓���Ȃ��Â��L���ÂƂ���B�n����- ���_�a�@-�L���Â̘A�g�́A���҂ɂƂ��Ă��ǂ���ÂƂȂ�A��t�ɂƂ��Ă����`�x�[�V�����̍�����ÂɂȂ�\��������B���̗l�ȃV�X�e�����m�����邱�ƂŁA���Â�����O�Ȉ�A���Ȉ�A���ː����È�̎u�]�҂������邱�Ƃ�Ɋ��҂��Ă���B
���Î��сi2009�N�R�������_�j�Ǝ��Ê�̉���
���@���@����@���Y
2003�N�S����ʐf�ÊJ�n���獡�N10���܂ł̖�T�N����2339���̊��҂���Ɏ��Â��s���Ă��܂����B
�N�x�ʎ����ʓ���
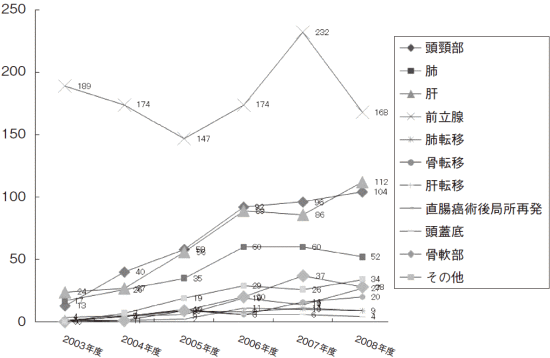
���Ώێ����ƈ�ØA�g
�@2008�N�x���O���B���ł������A�ȉ��A�̂���A������A�x����̏��Ɏ��Â��s���Ă��܂��B���݁A�_�ˑ�w�̎��@��A�ȓ��O�Ȋw�Ɗ̒_�X�O�Ȋw�̈�t���A�e�X�T�P�Z���^�[�̔��ΐE���Ƃ��ċΖ����Ă��܂��B������Ɗ̂��Ґ��͔N�X�����������܂����A���̗l�Ȉ�t�Ԃ̈�ØA�g�����Ґ������ɂȂ����Ă�����̂ƍl���Ă��܂��B |
|
���Ê��Ґ��̔N�����ځi2009�N3 ���F2639��j
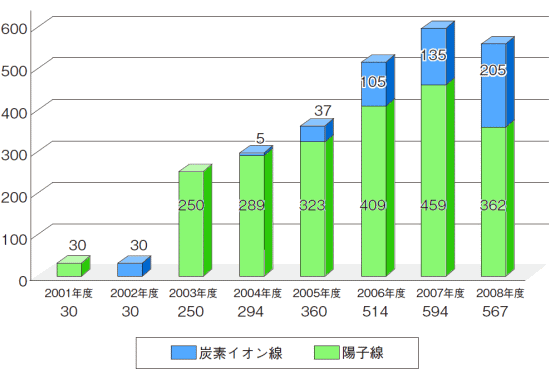
���ŋ߂̕ω�
��N�x�̊��Ґ���567���ł����B�g�p��������͗z�q���ɔ�גY�f�C�I�����̊������������Ă��܂��B
�@�_�ˑ�w�����łȂ����̈�Ë@�ցi�s�������a�@�A�s�����ː��ȃN���j�b�N�j�Ƃ̊Ԃł��A��t�Ԃ̈�ØA�g���i�݂� ����܂��B
�@���������łȂ������A�i�s����܂őΏۂƂȂ邱�Ƃ������Ȃ�A���X�ɓK�����g�債����܂��B���Ƃ��ΐi�s�̂��� �ɑ��郊�U�[�o�[�������p��A�Ǐ��i�s�X����ɑ��čs���Ă���R����܂p�������q���Ö@���s����悤�ɂȂ��Ă��܂����B |
|
���ŋ߂̎��Ð���
������
�@�Ǐ��i�s���������߂܂��B�ŋ߂̐��т́A�������F��i48��j�̂Q�N�Ǐ����䗦�F86���A�Q�N�������F52���A�B�l�X�E����i24��j�͊e�X85���A89���ł����B���W��Z���i41��j�Ɍ��肵�������ł͊e�X66���A85���ł����B������i�z�q���A�Y�f�C�I�����j�Ƃ�16��܂���26����̗p���A��������݂܂ł̏Ǝ˖@���p�����܂��B
�x����
�@I ���x����i80��j�̂R�N�Ǐ����䗦�F82���A�R�N�������F75���ł����B�ŋ߂ł͋��ǂɐZ�������Ǐ��i�s�x����̎��Â��s���Ă��܂��B�z�q���ƒY�f�C�I�����̎��Ð��тɍ���F�߂Ă��܂���B
�̂���
�@�̂���i290��j�̂R�N�Ǐ����䗦�F89���A�R�N�������F67���ł����B�z�q���ƒY�f�C�I�����̎��Ð��тɍ���F�߂Ă��܂���B�ő�14cm �̑傫���̂���܂Ŏ��Â��Ă��܂��B�������A�����Ȃ���̂ق����Ǐ����䗦�͍����X����F�߂Ă��܂��B
�O���B����
�@�O���B����i290��j�̂T�NPSA ���䗦�F88���A�T�N�������F97���ł����B���f����PSA �̒l�͗\������肷����q�ł��B���f����PSA �l���Sng/ml�ȉ��̏ꍇ�A�T�NPSA ���䗦��100���ł����A4.1-10.0ng/ml �ł�97���A10.1-20.0ng/ml�ł�87���A20.1�ȏ�̏ꍇ��70���ƂȂ��Ă��܂��B���Ì�̒����o���S���A���A�͂U���ɔF�߂܂����A���q�����Â͗L�p�Ȏ��Ö@�ƍl�����܂��B |
|
���Ɍ������q����ÃZ���^�[�ɂ����鎡�Ê�ꗗ�i2009�N�j
| �@�ہ@ |
�C�I����� |
�� |
| ������ |
�z�q |
60.8GyE�^16��^3.2�T�i3.8GyE�^��j |
| ������ |
�z�q |
70.2GyE�^26��^5.2�T�i2.7GyE�^��j |
| �x��^�x���� |
�z�q |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �x��^�x���� |
�z�q |
66GyE�^10��^2�T�i6.6GyE�^��j |
| �]�ڐ��x��� |
�z�q |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �]�ڐ��x��� |
�z�q |
64-68GyE�^8��^1.6�T�i8.0-8.5GyE�^��j |
| �c�u��� |
�z�q |
70.2GyE�^26��^5.2�T�i2.7GyE�^��j |
| �̂��� |
�z�q |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �̂��� |
�z�q |
66GyE�^10��^2�T�i6.6GyE�^��j |
| �����Ǘאڌ^�̂��� |
�z�q |
76-84GyE�^20��^4.0�T�i3.8-4.2GyE�^��j |
| �����Ǘאڌ^�̂��� |
�z�q |
76GyE�^38��^7.6�T�i2.0GyE�^��j |
| �]�ڐ��̎�� |
�z�q |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �]�ڐ��̎�� |
�z�q |
64-68GyE�^8��^1.6�T�i8.0-8.5GyE�^��j |
| �̖啔�_�NJ� |
�z�q |
76GyE�^20��^4.0�T�i3.8GyE�^��j |
| �������X���� |
�z�q |
60.8GyE�^16��^3.2�T�i3.8GyE�^��j |
| �������X���� |
�z�q |
70.2GyE�^26��^5.2�T�i2.7GyE�^��j |
| �������X���� |
�z�q |
50GyE�^25��^5.0�T�i2.0GyE�^��j |
| �t���� |
�z�q |
70.4GyE�^16��^3.2�T�i4.4GyE�^��j |
| �t���� |
�z�q |
76GyE�^20��^4.0�T�i3.8GyE�^��j |
�O���B����T-�U��
�iA�Q�F�\��ǍD�Q�j |
�z�q |
74GyE�^37��^7.4�T�i2.0GyE�^��j |
�O���B����T-�V��
�iB�Q�F�\��s�njQ�j |
�z�q |
MAB�Ö@�{74GyE�^37��^7.4�T�i2.0GyE�^��j |
�O���B����PSA>50ng/m
�il C�Q�F��PSA�Q�j |
�z�q |
MAB�Ö@�{74GyE�^37��^7.4�T�i2.0GyE�^��j |
�܂����N���Z���iT4�j
�O���B����T-�V��
�iD�Q�F�z�������s���Q�j |
�z�q
�z�q |
+MAB�Ö@
74-80GyE�^37-40��^7.4-8.0�T�i2.0GyE�^��j |
| ��������p��Ǐ��Ĕ� |
�z�q |
74GyE�^37��^7.4�T�i2.0GyE�^��j |
| �T���� |
�z�q |
74GyE�^37��^7.4�T�i2.0GyE�^��j |
| ����ᇁE���� |
�z�q |
70.4GyE�^16��^3.2�T�i4.4GyE�^��j |
| ����ᇁE���� |
�z�q |
70.4GyE�^32��^6.2�T�i2.2GyE�^��j |
| �]�ڐ�����ᇁE���� |
�Y�f |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �]�ڐ�����ᇁE���� |
�Y�f |
64-68GyE�^8��^1.6�T�i8.0-8.5GyE�^��j |
| ������ |
�Y�f |
60.8GyE�^16��^3.2�T�i3.8GyE�^��j |
| �d�v����ߐڌ^������ |
�Y�f |
70.2GyE�^26��^5.2�T�i2.7GyE�^��j |
| �x��^�x���� |
�Y�f |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �x��^�x���� |
�Y�f |
66GyE�^10��^2�T�i6.6GyE�^��j |
| �]�ڐ��x��� |
�Y�f |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �]�ڐ��x��� |
�Y�f |
64-68GyE�^8��^1.6�T�i8.0-8.5GyE�^��j |
| �c�u��� |
�Y�f |
70.2GyE�^26��^5.2�T�i2.7GyE�^��j |
| �̂��� |
�Y�f |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �̂��� |
�Y�f |
66GyE�^10��^2�T�i6.6GyE�^��j |
| �����Ǘאڌ^�̂��� |
�Y�f |
76-84GyE�^20��^4.0�T�i3.8-4.2GyE�^��j |
| �����Ǘאڌ^�̂��� |
�Y�f |
76GyE�^38��^7.6�T�i2.0GyE�^��j |
| �]�ڐ��̎�� |
�Y�f |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �]�ڐ��̎�� |
�Y�f |
64-68GyE�^8��^1.6�T�i8.0-8.5GyE�^��j |
| �̖啔�_�NJ� |
�Y�f |
76GyE�^20��^4.0�T�i3.8GyE�^��j |
| �������X���� |
�Y�f |
60.8GyE�^16��^3.2�T�i3.8GyE�^��j |
| �������X���� |
�Y�f |
70.2GyE�^26��^5.2�T�i2.7GyE�^��j |
| �������X���� |
�Y�f |
50GyE�^25��^5.0�T�i2.0GyE�^��j |
| �t���� |
�Y�f |
70.4GyE�^16��^3.2�T�i4.4GyE�^��j |
| �t���� |
�Y�f |
76GyE�^20��^4.0�T�i3.8GyE�^��j |
| ��������p��Ǐ��Ĕ� |
�Y�f |
70.4GyE�^16��^3.2�T�i4.4GyE�^��j |
| ����ᇁE���� |
�Y�f |
70.4GyE�^16��^3.2�T�i4.4GyE�^��j |
| ����ᇁE���� |
�Y�f |
70.4GyE�^32��^6.2�T�i2.2GyE�^��j |
| �]�ڐ�����ᇁE���� |
�Y�f |
52.8GyE�^4��^0.8�T�i13.2GyE�^��j |
| �]�ڐ�����ᇁE���� |
�Y�f |
64-68GyE�^8��^1.6�T�i8.0-8.5GyE�^��j |
| ���ǐ���� |
�z�q�E�Y�f |
�C�Ӂi����g�D�͑ϗe���ʈȓ��j |
�����Ê�ꗗ�i2009�N�j
�@2009�N�R��18���Ɍ������q����ÃZ���^�[���Ê����ψ�����J�Â��܂����B2009�N�ł͗z�q���ƒY�f���̔�r�����A�X����ɑ���V���Ȏ��Ê���o�ꂵ�����Ƃ������ł��B����A�]���̊�̂������ۂ̎��×Ⴊ�Ȃ������q�{����̊�͍폜���܂����B
������̕�����
�@���q�����Î{�݁E�m���̕��y��K�������̊g��ɔ����A����Ɋ��Ґ��̑������\�z����܂��B����܂ł̎��Ì��ʂ܂��A����w�A���S�m���Ȏ��Â����{�������ƍl���Ă��܂��B
�@�z�q���ƒY�f���̓K���m�����邽�߂̗Տ���r�����̎��{�B
�A��ØA�g�̂��ƁA�V���Ȏ����E�a���ɑ���W�w�I���Â̊g��B
�B���҃J���e�𒆐S�Ƃ����o�ߊώ@�V�X�e���̂���w�̏[���B
�C��b�����E�����w�����̐��i�B |
|
���q����ÃZ���^�[�ɂ�����Ō�t�ԘA�g
����Ō���Ō�t�@���{�@����
�P�D���Ì�̃t�H���[�A�b�v�̐�
�@���q�����Ì�̊��҂̌o�߂́A�Љ�a�@�ł���n��̕a�@�ƁA���q����ÃZ���^�[�̗��{�݂ŋ������t�H���[�A�b�v���s���V�X�e�����Ƃ��Ă��܂��B���Ì�̊��҂͏Љ�a�@�Œ���I�Ȍ�����f�@���A���̃f�[�^���厡�ォ��a����A���Z���^�[�ɑ��t���܂��B���Z���^�[�ł́A���������ƂɎ��Ì�o�߂̔c���A�Ĕ��̗L���A����p�̕ω��Ȃǂ����I�ɐf�Ă��܂��i�}�P�j�B
�@�Ō�t�́A���Ì�̂��܂��܂ȕs���⍢�育�Ƃɑ��鑊�k�Ή��A�܂����Ò��ɋN�������畆����������Ȃǂ̕���p�͎��Ì�����炭�������邽�߁A�d�b��[���ŃP�A�w�����p�����Ă��܂��B
�@����܂ŁA���q�����Ì�̊��҂̌o�߂�A����p�̕ω��ƑΏ��@�A������̍��育�ƂȂǂ͖��m�ł���A���Ҏ��g�����łȂ��A�������҂��T�|�[�g���Ă���Љ�a�@�̊Ō�t�ɂƂ��Ă��P�A�͎�T��ł������Ǝv���܂��B
�@���q�����Â������҂��A��ʐf�Â̊J�n�i����15�N�S���j����2500���ȏ�ƂȂ�܂����B�}�P�̂悤�ȃV�X�e���Ōo�ߊώ@���s�����ŁA���҂���̖���150���ȏ�̓d�b���k��A���҂��R�������ɑ��t���Ă��錟�����ʂ⊳�҃J���e�Ȃǂ�������Ì�̈�ʓI�Ȍo�߂��������c���ł���悤�ɂȂ�܂����B
�}�P�@���Ì�̃t�H���[�A�b�v�̐�
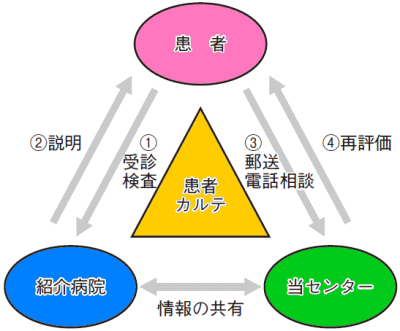 |
�Q�D���q�����Â̏�L�ƘA�g�E����
�@���Z���^�[�̊Ō�t�̎��̖����Ƃ��āA���q�����ÂƃP�A�Ɋւ�������s���A�n��̊Ō�t�ɂ��������������A�������Ȃ���P�A���ł��邱�Ƃƍl���Ă��܂��B���Ò��ɂ������L�Q���ۂ́A���Ì���������邱�Ƃ������A�ׂ₩�ȃP�A�ƈ�ÓI���u���K�v�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B���҂Ƃ��čĔ���]�ڂ̕s���A�ӊ��L�Q���ۂɑ��鑁�������ɂ��Ă��A�n��̕a�@�̊Ō�t�Ƌ������邱�Ƃł��g�[�^���I�ȃP�A���s����Ǝv���܂��B
�@���q�����Ì�̃P�A�͂܂��\���ɒm���Ă��Ȃ����߁A��N�x�́A���q�����ÂƊŌ�ɂ��Ă̏����s�����ƂƁA���҃P�A�������ōs����W������邱�Ƃ�ڕW�ɁA�ȉ��̂悤�Ȏ��g�݂��s���܂����B
�i�P�j����
�@�ߋ��ɗ��q�����Â������҂̎�ȏЉ�a�@��240�{�݂ɑ��A���q�����Ì�̃t�H���[�A�b�v�̐��A��Ȏ����̎��Ì�Ō�p�X�A����p�̃p���t���b�g��z�z�B
�i�Q�j�A�g�E����
�@���ҏЉ�̑����{�݂������K�₵�A�n��A�g���S���҂₪��Ō���Ō�t�ɑ��āA�Ō�A�g���˗��B��N�x�́A�����s�������a�@�A�P�H�ԏ\���a�@�A���Ɍ�������Z���^�[��K�₵�܂����B
�i�R�j�Ō쌤�C
�@�V�݂��ꂽ�쓌�k�z�q�����ÃZ���^�[�̊Ō�t�̌��C����
�A���Ɍ�������Z���^�[�̊Ō암�Ƌ��ÂŁA��N12 �����ː��Ō쌤�C���J�ÁB
���Ɍ����̊Ō�t��40 �������C�ɎQ���B
�B�Љ�a�@�̊Ō�t��ΏۂɁA���q����ÃZ���^�[�̌��w�ƌ��C�����B2009�N�P��16���A23���ɑS������v22�����Q���B
�C�����Ō���w�Z�̋����A�K���K��Ō�X�e�[�V�����Ō�t�̌��C����
�D�w���̌��w����
���Ɍ�����w��w�@���A����w��w�@���A�ߑ�P�H��w�Ō�w���w���Ȃǂ̎{���w�ƊŌ�̏Љ�
�y���C���e�z
�P. ���q�����Âɂ��āi���@���@���㏹�Y�j
�Q. ���Ìv��̌����E�Ō�ւ̊��������i���u�Ǘ��Ȓ��@�ԏ�@��j
�R. �Z�tIC�E�Œ��쐬��ʌ��w�i�S�����ː��Z�t�j
�S. ���q�����Âɂ�����Ō�i�Ō쒷�⍲�@�C�c������j
�T. ���q�����Ẫt�H���[�A�b�v�̐��i����Ō�CNS�@���{�����j
�U. ���u���w�i���ː��Z�p�Ȓ��@�{����j |
�R�@��̌�����𗬂̑��
�n��̊Ō�t�Ώۂ̗��q���Ō쌤�C��{�ݖK���ʂ��āA��̌�����𗬂̑���������Ă��܂��B�����̊Ō�t�͗��q�����Â͖��m�̗̈�ł��邽�߁A���q�����Â̓K���Ɋւ����ʓI�Ȃ��Ƃ�A���q���Ǝ��̃X�y�[�T�[�Ɋւ��鎿��Ȃǂ��o����܂����B
�����ɁA���ꂼ��̎{�݂ŗ��q�����Ì㊳�҂̃P�A���@�Ɋւ���Y�݂�����Ă����邱�Ƃ�������A�𗬂��ł������ƂŁA����܂Ŋ����Ă����^��̉����ɁA�����͖𗧂����ƍl���Ă��܂��B
�@���ɂ́A�t�H���[�A�b�v���@�ɑ��āA���҂ւ̉摜�ݏo���Ɋւ���Ɩ��I�ȕ��S�����邱�Ƃ�A���q���Ɗ��҂̂���肪�����Ȃ��Ȃǂ̖���N���邱�Ƃ�����܂����B�����������₪�A���R�̂悤�ɓ��X�s���Ă������Ì�̃t�H���[�̂�����ɂ��āA���߂čl����@��Ɍq����܂����B
�@���C�̃A���P�[�g�ł́A�u���Î��̌��w��A�a���A�o�ߊώ@�̑��k�������w���邱�Ƃɂ��A���q�����Â��C���[�W���ł���悤�ɂȂ����v�u���Ì�̊��ґ������߂��v�Ȃǂ̊��z��������Ă���A�Ō�t���g�����q�����ÂƊŌ�̗�����[�߂Ă��������ǂ��@��ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�S�@������
�@���������Ō�ԘA�g��ڎw�����炪������𗬂�ʂ��āA���҃P�A�ɂ��Ă̓d�b��Ō�f�Ï����̊��p�ȂNj����ł��邱�Ƃ������Ă������Ƃ��������Ă��܂��B���Ì�͊��҂ɒ��ړI�ȃP�A�����@����Ȃ��Ȃ�܂����A���҂����Â��Ă悩�����Ǝv����悤�ɁA�p���Ō삪�X���[�Y�ɍs���閧�ȘA�g������Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�@����Ƃ��A�n���Ȋ����ł͂���܂����A���Z���^�[�̊Ō�t����A���낢��Ȃ��ƂM���Ă��������Ǝv���܂��B
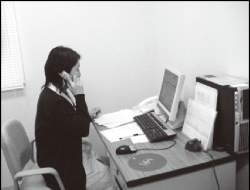
�o�ߊώ@�̓d�b���k�̗l�q |

���q���Ō쌤�C�̗l�q |
�쓌�k����z�q�����ÃZ���^�[�̊J�ݔ��N��U��Ԃ�
���c�@�l �]�_�o����������
���� �쓌�k����z�q�����ÃZ���^�[
�������@�і�@���Y
�ݗ��̌o��
�@�o�c�҂ł���n糗������́A���{�Љ�͍�����i�݁A����ɂ�鎀�S�҂��������鏫���A�u�炸�Ɂv�u����p���قƂ�ǂȂ��v����������Ƃ������҂���ɂƂ��ėD�������Â��Љ�I�v���ł���ƍl���Ă��܂����B �����āA�������������ɂ͗z�q�����Â��ł��K���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���ƒT���Ă��܂����B
�@����Ȓ��A2004�N12���A���Ɍ������q����ÃZ���^�[���{���w���A�z�q�����Â̕K�v���E�d�v���A�\���Ȃǂ̔F���āA2005�N�U���ɂ́A�z�q�����Î{�݂ł���
�A�����J���O���{�X�g���ɂ���MGH�i�}�T�`���[�Z�b�c�����a�@�j���J���t�H���j�A�ɂ���LLUMC�i���}�����_��w���f�B�J���Z���^�[�j�Ȃǂ����@���A�z�q�����Î{�݂̌o�ϐ������Ă������݂̉\���̔��f���ł��܂����B
�@���̌�A���Ɍ������q����ÃZ���^�[�̌��ӂɂ��X�^�b�t����⎡�ØA�g�̋��肪�A�ŏI����v���ƂȂ�A�z�q�����ÃV�X�e����������Ɏ���܂����B
�V���ȑD�o
�@�J�݂܂ł̊ԁA�����m�ہA���Ñ��u�d�C���[�J�[�Ƃ̒����A�X�^�b�t�m�ہA�����Ȋw�Ȃւ̎g�p���\���ȂǁA�����グ�Ɍ����Ď�X����Ȗ�������A���]�Ȑ܂�����܂������A2008 �N10 ���P���ɃI�[�v���ɑ��������A����17 ���ɂ͂P��ڂ̎��Â��J�n����܂����B
�@�ȑO���瑍���쓌�k�a�@��A��Ȃŗ\������Ă���O���B���҂���𒆐S�Ɏ��Â��X�^�[�g���A�����͎��R�f�Ái���z3,000 ��~�j�ōs���A�P��15 ���ɂ�10 ���̎��Î��т��グ�A���k�����ǂ։��x�������^�сA�Q������̐�i��Ái2,883 ��~�j���F�߂��邱�ƂɂȂ�܂����B�������A���̐S��́A���V�̒��A�s�j�i�Z���^�[���j�͒�������F����̓��}�g���D�o�����A�s����́A���ɈÉ_�Y�����̒��֓˓�����悤�ȃC���[�W�ł����B
�@���̌�A���҂���̖₢���킹��A�����O����̊O���E�Љ�������n�߁A�S���W���ɂ́A100 �l�ڂ̎��Â��X�^�[�g���܂����B
�@���̂悤�Ɋ��҂��}�����钆�A�x�b�h�������Ƃ����Ԃɖ����i19 ���j�ƂȂ�A�R������ÂƂ̕��p���҂������A�a�����p���K�v�s���ƂȂ�킯�ł����A�ߗׂ̃z�e���𗘗p���Ă��������A�~�ނ��ʉ@�ł̎��Â����肢���Ă���Ƃ���ł��B���ɂ́A����100km �ȏ�̋������Ԃł̈ړ�������Ă���������āA���Î��Ԃ̗\�����@�̒����ɂ��ꗶ���Ă���ł��B
�@����ŁA��Î��̂̐S�z���₦�܂���B���̂��߁A��È��S��⎡�Âɔ����i���Ǘ����ŏd�v�ƍl���A��w�����m�𒆐S�Ƃ����i���Ǘ��̑̐��������s���A���x�Ǘ��Ǝ��̖h�~�ɉs�ӓw�߂Ă��܂��B
���Â̏[���Ɍ�����
�@�v���W�F�N�g�J�n����A�킸���R�N�̊��ԂŃI�[�v�����܂������A��ɐV������肪�������A���̉������Ȃ���Ύ��ɐi�߂Ȃ��Ƃ������Ƃ̐킢�̓��X�ŁA�f�ÊJ�n����A�X�Ȃ鑽���̖�肪���X�������A�����킢�̓��X�͑����Ă��܂��B
�@��X���s���邱�Ƃɂ͌��E���L��܂����A�s�j�Z���^�[���𒆐S�ɁA���҂����S���Ď��Â�����悤�A��È��S�̐������A�i���Ǘ���O�ꂵ�A���҂���Ƃ̘A���̐��̐�����A�O�ꂵ���E���ւ̏��ɂ����S�����R�~���j�P�[�V�������Ƃ��悤���g��ł�
�܂��B
�@�܂��A���Ɍ������q����ÃZ���^�[�Ƃ̎��ØA�g�𖧂ɂ���ƂƂ��ɁA�אڂ���n�悪��f�ØA�g���_�a�@�i�����쓌�k�a�@�j�⍂�x�f�f���ÃZ���^�[�ł���i�쓌�k��ÃN���j�b�N�j�Ƃ���̂ƂȂ�A���E�ɊJ���ꂽ�g���ԏ��̗z�q�����Î{�݁h�Ƃ��ď[�������z�q�����ÃV�X�e���̍\�z�Ɍ����A�E����ۂƂȂ��Ď��g��ł��������Ƌ����l���Ă��܂��B

���q����ÃZ���^�[�ɕ��C�����`�l�Ƃ̂Ȃ���`
���ː��Ȉ㒷�@���n�@���K
�@���̂S�����瓖�Z���^�[�ɕ��C���Ă��܂��B�ȑO�͍����a�@�@�\�̐_�ˈ�ÃZ���^�[�i�_�ˎs�{����j�ŁA���ː��ȋƖ���ʂ��s���Ă��܂������A���ː����Âɂ͏T�ɂP�����x�]�����Ă��܂����B
�@���̂��сA���Z���^�[�ɍ̗p����A���ː����Â̌o����ς݁A�����A���ː���ᇈ�Ƃ��āA���ÂɌg����Ă�������ƍl���Ă��܂��B
�@���q���Ƃ�������ȕ������������������ː����g�p���鎡�Â�ڂ̂�����ɂ��āA����ɐN����ꂵ��ł��銳�҂���ɑ��āA�Ő�[�̋@����g�p���A��ËZ�p����g���āA�����ǂ����鎡�ÂƂ��Ċ����ƂƂ��ɁA���͂������Ă���܂��B
�@���܂ň�ÂɌg����Ă��āA�������������Ƃ́A�u�l�Ƃ̂Ȃ���v����Ƃ������Ƃł��B���҂���ɂ��\���Ȑ������s���A�����Ɣ[�������Ē����A�ǂ��R�~���j�P�[�V�������Ƃ�āA�M���W��z�����Ƃ����Âɔ��ɏd�v�ƍl���܂��B���҂���̋��͂Ȃ����āA���Â𐋍s���邱�Ƃ⎡�Â̌��ʂ��]�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�@�܂��A���Â̓`�[����Âł��B���͂̃X�^�b�t�A���Ȃ킿��t�A�Z�t�A�Ō�t�A��t�A�����Ɩ��ɘA�g���Ƃ�A��̎��Ái�����ǂ����邱�Ɓj���s�����Ƃ��ł��܂��B���̉ߒ��ł��ǂ����Ö@��͍����邱�Ƃ⊳�҂���̕a�Ԃ��f������A���Ìv��̏C���A����̂��Ƃɂ��Ęb����������A���҂���̊��𐮂��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B���̍ہA���͂̃X�^�b�t�Ɨǂ��W��z���Ă���Ɣ��ɃX���[�Y�����̂��Ƃ��s�����Ƃ��ł��܂��B
�@������A�u�l�Ƃ̂Ȃ���v���ɂ��Ȃ���A���q�����Â̔��W�Ɋ撣���čs������ƍl���Ă��܂��B
�S�N�Ԃ�U��Ԃ��ā`�a�@�̐i���`
���ː��ȑO�㒷�@�{�e�@���
�@���q����ÃZ���^�[�ɂ́A2005�N�S��������Έ�t�Ƃ��āA2006�N�S�����炱�̂R���܂ł̂R�N�Ԃ́A��Έ�Ƃ��ċΖ����܂����B
�@���q����ÃZ���^�[�́A���̂S�N�Ō��I�ȕω��i�i���j�𐋂����Ǝv���܂��B�����Ζ����n�߂�2005�N�Ƃ����̂́A�Y�f�C�I�������Â���ʐf�É����ꂽ����ŁA�z�q�����ÁA�Y�f�C�I�������Â̗����̎��Â��s����悤�ɂȂ��������ł����B���q�����ÂƂ������̂����ԂɍL�܂�A���X�Ɋ��Ґ��������A�܂��A���ː��Z�p�Ȃ̐{��Ȓ������S�ƂȂ��Đ����i�߂�u�v�Z�@���x���v�u�ێ�l�b�g���[�N�v�u�ێ番�U�Ǘ��v�̃v���W�F�N�g�̐��ʂ��オ��A�P�N��ʂ��ăR���X�^���g�ɑ����̊��҂�������Âł���悤�ɂȂ�A2006�N�ɂ͎��Ê��Ґ����P��60�l���z���A�N��514�l�ƂȂ�܂����B
�@2007�N�x�ɂ͎��Ê��Ґ���594�l�ƂȂ�̂ł����A���̔N�x������A����܂ł͑S�Ĉ�t���s���Ă������q�����Ìv��Ɩ��ɁA��w�����m���Q������悤�ɂȂ�A���Ìv��ɐ�]���邽�߁A���Ìv����X�ɗǂ����̂ɂȂ����Ǝv���܂��B���̎������疈����P���ԁA�O���ɍ��ꂽ���Ìv��̐���ɂ��đ��E�킪�W�܂��ēO��I�Ɍ�������J���t�@�����X���n�܂�܂����B�܂��A�f�Õ��ː��Z�t�����Ìv��Ɩ��Ƀ��[�e�[�V�����Ōg���悤�ɂȂ�A���Ìv�����鑤�̗���ɗ������摜�B�e�����Ă����悤�ɂȂ�܂����B�����炭�A���Ìv��Ɩ��̌o�������ۂ̏ƎˋƖ��ɂ���������Ă���Ǝv���܂��B
�@����ɁA�_�ˑ�w�a�@�̒_�X�O�ȂƎ��@��A�E���O�Ȃ���̔��Έ�t���Ζ�����悤�ɂȂ�A���ȂƂ̖��ȃR�~���j�P�[�V�����ɂ��A���q�����Â̎��̍�������i�オ�����Ǝv���܂��B2008�N����͊̑�����≻�w�Ö@�ɏڂ�����t�������A�̑�����ɑ��ẮA�l�X�ȃ��_���e�B����g�������Â�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����A�ꕔ�̎����ł́A���w�Ö@�p�������q�����Â��J�n���Ă���܂��B�܂����q�����Â̎�_�ł���}�����E�ӊ��̔畆���ɂ��Ă��A��t�E�Ō�t�Ŕ畆�P�A�S���`�[�������A�V���ȗ\�h�@�E���Ö@���J�����A���̐��ʂ��o����܂��B
�@���҂���ɂ��ǂ���Â�������Ƃ����C�����͂S�N�O���ς��Ȃ������Ǝv���܂����A�ȑO�͊e�X�̐E��̐l���e�X�̗���Ŋ撣���Ă����̂��A���͑S�X�^�b�t����ۂƂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�@���͂��̂R�����ŕ��Ɍ������q����ÃZ���^�[��ސE���A���݁A�_�ˑ�w��w�������a�@���ː���ᇉȂ̏����ƂȂ�܂������A�S��������T�P�`�Q��A���q���ŋΖ������Ă��������Ă��܂��B����Ƃ���낵�����肢�������܂��B
���Î����̊g��ɑ������Ō�Ȃ̎��g��
�Ō�Ȓ��@���{�@�m�q
�@���@�Z���^�[����13�E14�N�̎������o�āA����15�N����ʐf�Â��J�n�����N�łV�N�ڂ��}���܂��B�ߔN�͗��q�����Â��銳�҂̑w�����L���Ȃ��Ă��Ă���A�Ō�P�A���Ώۂɍ��킹�ω������Ă��������ɂȂ��Ă܂���܂����B�����A���@���҂̑唼���߂Ă����O���B�����QOL�iQuality of life�j�̒ቺ�����Ȃ����Ê������\�ł��邱�Ƃ���ʉ@�ɐ�ւ�����܂��B���@�́A���E�́E�x�E����̎��Â⎝�a�̂�����Ȃǎ��Ò��ɂ��ׂ₩�ȊŌ�P�A��K�v�Ƃ��銳�҂�����Ă��܂��B�܂��A����21�N�P������͍R����܂ɂ�鉻�w�Ö@�p�������Â��V���ɓ�������铙�A���q�����Â͔��W���Ă���A���Õ��@��ΏۂƂȂ銳�҂̏��l�ς�肵�Ă��܂��B���̂悤�ȏɑ������A���Җ����̏[����ڎw�����Ō�Ȃ̎��g�݂̊T�v���Љ�܂��B
�� �N���j�J���p�X�̐ϋɓI���p�ƃP�A�`�[�������̐��i
�@��ʐf�ÊJ�n�Ɠ����ɑS�Ǘ�ɂ����ăN���j�J���p�X�i�ȉ��u�p�X�v�j�����p���A���̐��͂V��ނ���40��ވȏ�ɑ����Ă���A���Éߒ��̒��ň�t����̊��ҁE�Ƒ��ւ̃C���t�H�[���h�R���Z���g�͖ܘ_�̂��ƁA�Ō�t�̓p�X�Ɋ�Â���̓I�ł킩��₷�������E�w����S�����Ă��܂��B�Ώێ����̊g��ɂ��A�p�X�ɂ��W�����P�A�����H���鑤�ʂƊ��҂̐S�g��c�������ʓI�ȊŌ삪���߂��܂��B�Ǝ˕��ʂ���ʓ��A���Ìv��ɕύX���������ꍇ�ɂ́A�d�q�J���e��ő��₩�Ƀp�X�̏C���E�lj����\�ŁA�l�ɑ��������ÁE�P�A�}�b�v�Ƃ��āA�D�]�Ă��܂��B�܂��A���q�����Âɔ����������E�畆�����̍����ǃP�A�ł́A���̃Z�N�V�����Ƌ����E�A�g���A���҂���̓I�ɃP�A�ɎQ���ł���悤�畆�P�A�E���o�P�A�`�[�����������H���Ă��܂��B�����̂��Ƃ����@�`�މ@��̊��҂̃Z���t�P�A�̑��i�Ɍq�����Ă��܂��B
���n��{�݂Ƃ̘A�g�Ƒމ@��̃t�H���[�A�b�v�V�X�e��
�@���Â��銳�҂̋��Z�n�͖k�͖k�C�������͉���ƑS���K�͂ł��B�������𗝗R�ɓ��@��]���銳�҂�S�Ď���邱�Ƃ͍���ł���A����18�N����ߗׂ̂Q�a�@�Ƃ̘A�g�ɂ�肻������̒ʉ@�V�X�e�����m���ł��܂����B���̌��ʁA���Ñ҂����Ԃ̒Z�k�E�×{���̊m�ۂɂ��A�����E���S�̐����Ԃ��Ă��Ă���A�މ@��́A�o�ߊώ@�`�[�������S�ƂȂ�d�b���k�ɉ����Ă��܂��B�������Ȃ���A�ʐM��i�ɂ�鉓�u�ł̊Ō�x���ɂ͌��E������A�����E�S�����ʂ���x������n��̎{�݁E�Ō�t�Ƃ̘A�g���d�v�ɂȂ邱�Ƃ�Ɋ����Ă��܂��B
�@����́A�X�Ɍ��ʓI�Ȍp���Ō삪�ł���悤���̘A�g�V�X�e����]������ƂƂ��ɘA�g�a�@�̊g���}�肽���ƍl���Ă��܂��B���̂��߂ɂ��A��i��Â�S���Ō�t�Ƃ��č\�z�������I�Ȓm���E�Z�p��]���E�������A�L�����M���Ă������Ƃ��s���ł��B���N�x�́A�@�O�Ō�t��ΏۂƂ��錤�C��J�Â�֘A�w��ւ̔��\���s�Ȃ��ƂƂ��ɁA���_�a�@�⑼�̗��q���{�݂Ƃ̌𗬂�[�߁A�`�[������ۂƂȂ��含�̍�������Ō��W�J���Ă����ӋC���݂ł��B
��W��a�@�^�c���b�� �J��
�a�@�^�c�ɓ������āA�����̑��l�Ȉӌ������߁A�����̈�Ãj�[�Y�ɔ��f�����邽�߁A�ψ��S���i�V���j�Q���̂��ƁA�^�c���b��J�Â���A�����ȋc�_�����킳��܂����B
�J����
����21�N �R���Q���i���j
15���` 16��30�� |
��ȓ��e
�E���q�����Â̕ی��K�p�����ɂ���
�E�ی��K�p���ʂɂ���
�E�z�q�����Â̊����̌����ɂ���
�E�Z���^�[�Ƃ��Ă̎��Õ��j�ɂ��� |
|
�Z�J���h�I�s�j�I�������̉���
����21 �N�T���P������A�����̌n�����Ԓ�z���i�ی��K�p�O�j�ƂȂ�܂��B
|
| ���ʒk���� |
30 �������� |
10,500 �~ �i�ԏ��쐬�������܂ށj |
|
15 �����ߖ� |
2,250 �~ ���Z |
|
|

