���Ɍ������q����ÃZ���^�[
�j���[�X���^�[No.29
December 2009
CONTENTS
�����@���ɂ̗��q������
�����@�z�q���ƒY�f�C�I�����̎��Î���
�����@��V���a�@�w��ɎQ������
�����@�Ǝˊ��Ԓ��̖����̂ЂƂƂ�
�����@���q����ÃZ���^�[�ɕ��C���ā`�l�Ƃ̂Ȃ���`
�����@���������H�ׂ���悤��
�����@���Ɍ������q����ÃZ���^�[�Ō��C����
�@�@�@�@�@�@
�����@��Ãg�s�b�N�X
���ɂ̗��q������
���Ɍ������q����ÃZ���^�[
�@���@�H��@�Ǖv
�@���Z���^�[�ł́A2001�N�ɗz�q�����Â̗Տ��������s���A2002�N�ɒY�f�C�I�������Â̗Տ��������s���Ă��܂����B
�@2003�N�����ʐf�Â��J�n���A�悤�₭���N�x�A�P�N�x�������������߂�ɂ���A�V���ɗ��q�����Î{�݂���������Ă�����ւ̎Q�l�ɂȂ�Ƃ����l���ŁA���݂܂ł̌o�܂ƍŋ߂̏��A�傫���R���ɕ����Đ������Ă݂܂����B
�P�j��1���i��ʐf�Â̊J�n�F2001-3�j
�@��ẤA�@�ɏ]���s���܂��B�@�ł́A�V�K�̈�Ë@��͗Տ��������s���A���S����L�������Ɋւ��č��ɓ͂��o���܂��B���F�����A�������[�J�[�́A���̋@��̔̔����ł��A��Ë@�ւ͂��̋@��ň�Â��ł���悤�ɂȂ�܂��B�Q�N�Ԃ̗Տ������́A��Â����邽�߂̏������Ԃł����B
�@2003�N�̈�ʐf�ẤA�Տ������̑Ώۂł��������z�����A�x����A�̂���A�O���B���Ŏ��Â��X�^�[�g���A�S�����@�̏�A�T�d�Ɏ��Â��s���Ă��܂����B
�Q�j��Q��(���u�����̌���F2004-6)
�@���Z���^�[�̏ꍇ�A�N��640���ȏ�̎��Â�������������A�p���I�ȉ^�c���\�ł��B�������_�̑��u�́A�����{�݂̏��^�łł���A�P��������A�ʏ�̋Ζ����ԓ��Ŗ�30���̎��Â����ł��܂���ł����B�P��30���́A�N�Ԃɂ���Ζ�300���ł��B600���ȏ�̎��Â�����ɂ́A�����̑��u�ł͂Q��オ�K�v�ŁA���ہA�X�^�b�t�̊撣��ŁA�P��50���̎��Â��������Ƃ�����܂����B�������A�Ō�̊��҂���̎��Â͖�̂W�����ƂȂ�A�ƂĂ��撣�肾���ł͑ʖڂ��Ɣ��f���A�P��60���̎��Â��Ζ����ԓ��ɂ���ڕW�𗧂āA���ː��Z�p�ȁA���u�Ǘ��ȕ��тɃ��[�J�[���܂��A���u�̌���������ɂ��ēO��I�ɍl���Ă��炢�A���̌��ʁA10���̕��i�Ɣ��������Q���A�f�[�^�[�x�[�X�����܂����B
�@�W�����C���e�i���X����P��������A���̊ԁA���Â��ł��Ȃ������̂��A2006�N�x����A�f�[�^�[�x�[�X�̉�͂ŁA�e���̕��U���C���e�i���X�ɕς��邱�Ƃ��ł��A����ɂ��A�N�Ԃ�ʂ��Ă̎��Â��\�ƂȂ�܂����B
�@�P��30���̎��Â�60���ɂ��邽�߂ɁA����̎��_�Ń��[�J�[���w�����A���u�̌�������i�߁A����ɂ�胁�[�J�[�ł́A10�ȏ�̓������Ƃ錋�ʂƂȂ�܂����B�Ⴆ�A�z�q�����Â̂X������n��14���܂ōs���A�Y�f�C�I�����ɐ�ւ���̂ɁA�P���Ԃ������Ă����̂��A���ł͖�10���ƂȂ��Ă��܂��B�����������ʁA�ʏ�Ζ����ł̎��Ê��Ґ���60���ɂȂ��Ă��܂��B
�R�j��R���i�`�[���͂̌���F2007-9�j
�@�ێ番�U�����ɂ��A�����̊��҂���̎��Â��ł���悤�Ȃ������ƂŁA���̎��ÂŎ����Ȃ����҂���̐��������Ă��܂����B
�@���̊ԁA�`�[����Â̎��̌����ڕW�Ƃ��āA���Ɏ��Ìv���O��I�ɉ��P���Ă��܂����B���ː��Z�t�A��w�����m�A��t�̋����Ŏ��Ìv����쐬����ƂƂ��ɁA�O���B�ȊO�̂���ł́A�z�q���ƒY�f�C�I�����̂Q��̎��Ìv��쐬��O�ꂷ��ƂƂ��ɁA�����A���Ìv��Ɋւ���J���t�@�����X����ÃX�^�b�t�ōs���A�Q��̌v����r���A�c�_�𑱂��Ă������ƂŁA���Ìv��Ɋւ���`�[���͂����ɍ����Ȃ��Ă��܂����B���ː��Z�t���w�����m���A�Տ��ł̖��_�𗝉����A��t�͕����I�Ȗʂł̎��Ìv��̗������i�ƍl���Ă��܂��B
�@�܂��A�Ǝ˂��邽�߂̍X�߃��b�J�[�ݒu�ɂ�钅�ւ����X���Ȃ������A�Ǝ˂̌��������i�݁A�B2009�N�W���ɂ͂P��99���̎��Â�B�����܂������A18�����܂łɑS�Ă̎��Â��I�����Ă��܂����B
�@��P�A�Q���ł́A�O���B���̊��҂�������@���Ă��������Ă܂������A���݂́A���̎��ÂŎ����̂�����Ȏ�p�s�\�ȋǏ��X����⌌�ǂɂ܂Ŏ�ᇂ̐Z�������̂���̊��҂������A���@�͉������Ă��������Ă��܂��B���̂悤�Ȑi�s����ł́A���w�Ö@�̕��p���K�v�ŁA�Ō�t�A��t�̗����Ƌ��͂̂��ƁA���Â�i�߂Ă���̂������ł��B
�S�j����̓W�J
�@���q�����ẤA�n�[�h�ł��鑕�u�ƃ\�t�g�ł���f�Â���Ȃ�V�X�e����Âł���A�n�[�h��ǂ����邱�ƂŁA�����̊��҂����Âł��܂��B���҂���ɂƂ��Ĉ�Ԕ߂����̂́A���Â������ɂł��Ȃ����Ƃł��B���܂ł̑��u�V�X�e���̉��P�́A100���̎��Â�ʏ�Ζ����Ԃ�菭���������邱�ƂŒB�����A�����̊��҂���ɑ҂߂��݂�^���Ȃ����Â���Ă��܂����B�\�t�g�ł���f�Öʂł̉��P�𑱂��邱�Ƃ́A����ȋǏ����̎������\�ɂ��܂��B
�@������A������������ƂƁA���̎��Â��y�Ɏ����邱�Ƃ����q�����Â̑傫�ȓ����ł���A�������������S�ŗǍD�Ȉ�Â̒𑱂��Ă����ƂƂ��ɁA���ẤA��Ñ��Ɗ��ґ����A��܂������邱�Ƃł����ʂ��o��ƍl���Ă���A�������������ׂ��w�͂����Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�z�q���ƒY�f�C�I�����̎��Î��сi2009�N�㔼���F9�������_�j
���@���@����@���Y
2009�N�X�������_��2976���̊��҂���ɑ��Ď��Â��s���Ă��܂����B
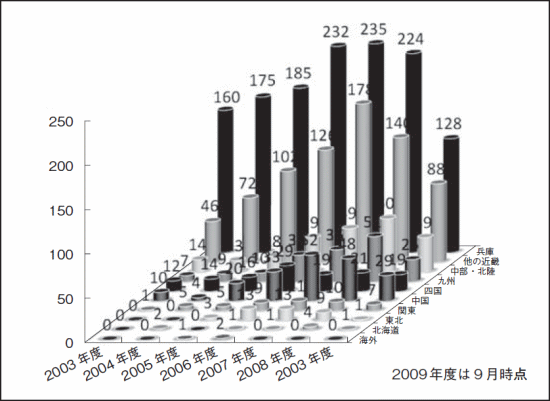

�����Â�������X�̋��Z�n��
�@2003�N�̈�ʐf�ÊJ�n���_�́A���Ɍ��̊������U�����A�ߋE�n���ɂ��Z�܂��̕��X�i���Ɍ����܂ށj�̊������W�����Ă��܂������A�N�X�A�m���x�̐Z���ƂƂ��ɁA���̒n�����痈���������������܂��B���݂ɁA21�N�x����i�S�`�X���j�̊����́A���Ɍ�����S���A�ߋE�n���i�i���Ɍ����܂ށj�̊������S�̂̂Q�^�R���߁A�c��̂P�^�R���A�ߋE�n���ȊO�ŁA�����E�����E��B�E�l���̏��ŁA�����{�����S�ƂȂ��Ă��܂��B
|
|
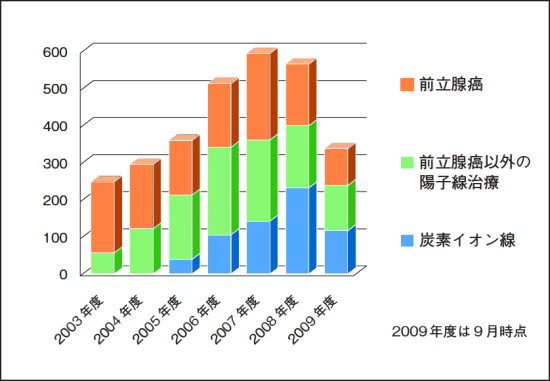

���Y�f�C�I�������Â̑����ƑO���B����
�@�O���B���͗z�q����p���Ď��Â��s���܂��B�O���B���ȊO�̎����̎��Â͗z�q���ƒY�f�C�I�����̂�������\�ł����A�ŋ߂ł͒Y�f�C�I�������Â����邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����B2007�N�x��藼�����p���Ď��Ìv����쐬����悤�ɂȂ�A��l�ЂƂ�̊��҂���ɍœK�Ȑ�����������I������悤�ɂȂ������ʂł���Ƃ����܂��B
�@�Ȃ��A�O���B���ɂ��Ă͖��N200���O��̎��Â��s���Ă���A�傫�ȑ����͂���܂���B
|
|
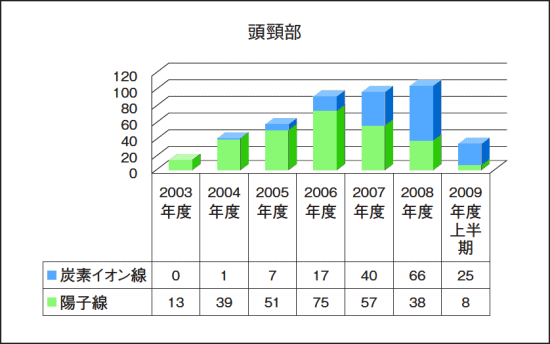

��������
�@���z�����Â͋ߔN�����X���ɂ���܂������A���N�x�̌����_�ł́A33���ƑO�N�x����⌸�����Ă��܂��B2007�N�x�ȍ~�A�Y�f���̎��Î��т������Ă��܂��B���Âɂ����ẮA���_�o�A�]�Ȃǂ̏d�v����ւ̕s�K�v�ȏƎ˂�����邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�܂��B�����ŗ�����̎��Ìv����쐬���Ă������ʁA�����d�v����߂��Ɏ�ᇂ�����ꍇ�́A�Y�f�C�I�������I�������p�x�������Ȃ��Ă��܂����B
|
|
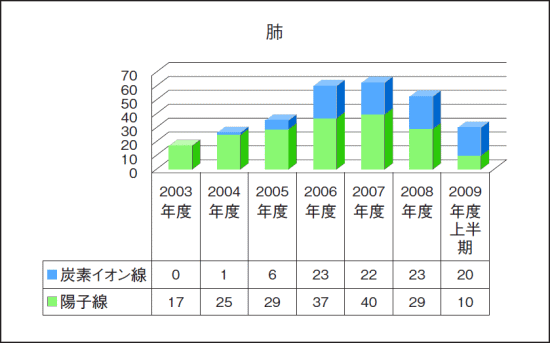

���x����
�@�x����͔N�Ԗ�60���̎��Â��s���Ă��܂��B�����͇T���x���ł��B�ߔN�͒Y�f�C�I������I�����邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂����B
|
|
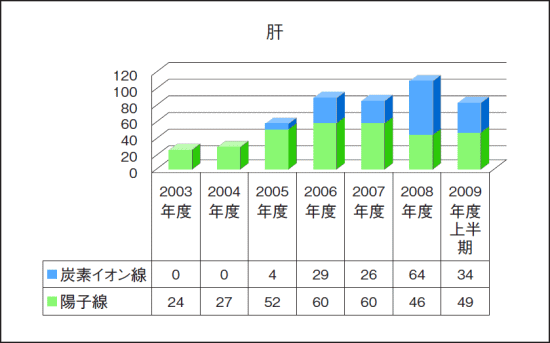

���̂���
�@��N�͔N��110���A���N�x�͏㔼���Ŋ���83���̎��Â��s���Ă���A���Ì����͔N�X�}���ȑ����X���ɂ���܂��B���ẤA��N�x���Y�f�C�I�������g�p���邱�Ƃ����������̂ɔ�ׁA���N�x�͗z�q���������Ă��܂��B�����ǂɗאڂ����ᇂ́A�����ǂ�ی삷��ׂ��A��茵���ō��x�Ȏ��Ìv�悪�K�v�ƂȂ�A���̌��ʁA�Y�f�C�I�������Â�I�����邱�Ƃ������Ȃ�܂����B
|
|
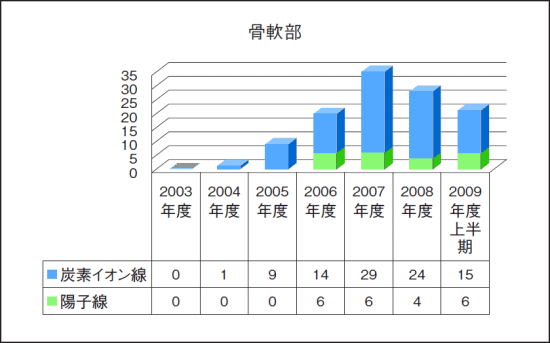

��������
�@�N�Ԗ�30���̎��Â����Ă��܂��B����̈悩�甭��������ᇂ́A�]���̕��ː��ɑ��Ē�R���̂����ᇂ������A�Y�f�C�I�������Â��s�����Ƃ������Ȃ�܂����B
|
|
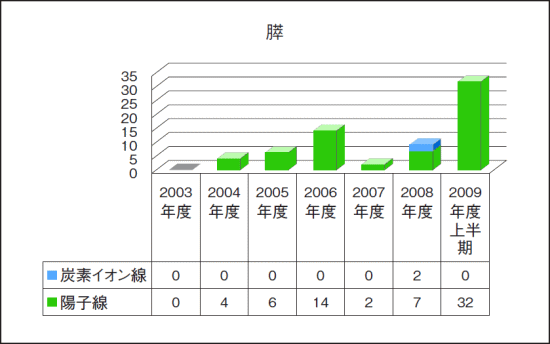

���X����
�@2009�N�x�ɓ���A���Z���^�[���X����̎��Â���������}���ɑ������Ă��܂��B�X���͈݁A�����A�咰�Ɏ��͂܂ꂽ�ʒu�ɂ��邽�߁A���Ƃ����q����p���Ă���ᇑS�̂ɍ����ʂ𓊗^���邱�Ƃ͕s�\�ł��B�����������I�ɍ����ʂ̗z�q�����Ǝ˂��邱�Ƃ͉\�ł��邽�߁A���N�P�����R����܂p�������Ö@���̗p���܂����B����A���Ð��т��ώ@���Ȃ���A�����S�Ō����I�Ȏ��Ö@�̊m����ڎw���܂��B
|
|
��V���a�@�w��ɎQ������
�����ے��@�R�d�@���i�i���^�c�ψ��j
�@����21�N�W��29���ɑ�V���a�@�w��b���w�ŊJ�Â���܂����B���̊w��́u�a�@�\�����v���i����v�̒��̈�ł���u���ǎ��Ȉ�Â̒v�̋�̓I�Ȏ��g�݂Ƃ��āA�]���A�E��ʂɎ��{����Ă����������\����{���������̂ł��B
�@�����a�@�œ����l�X�ȐE��̐E�����A�E��̕ǂ��Ĉꓰ�ɉ�A�S�̉�Ŋ�u���u���A���������e�E��ʂ̕��ȉ�ł��ꂼ������̋Ζ��Ŏ��g���P���ڂ�A�V���ȋZ�p���v�Ɍ��т��悤�Ȍ��r�̐��ʂ��|�X�^�[�E�p���[�|�C���g�Ȃǂ̃��f�B�A���g�����\���܂��B
�@�E��ʂ̕��ȉ�Ŕ��\���ꂽ�_���̒�����A�D�G�Ș_���ɂ͕a�@���ƊǗ��҂��܂������܂��B
�@����ɁA���̌�A�S�̂Ƃ��ăV���|�W�E�����s���A���ꂼ��قȂ闧��E�p�x��������̋^��_�Ȃǂ�b���������Ƃɂ��A���_�̒��o���ł���悤�H�v����Ă���w��ł��B
�@���́A���N�x�̊��^�c�ψ���C����X�^�b�t�̈�l�Ƃ��ĎQ�����܂������A�����͒��W�����ɏW�����A���U���S���Ƃ��Ē�����[���܂łقƂ�Ǘ������܂܂ŗ���҂���̖₢���킹�ւ̑Ή��A�ē��ɒǂ���ȂǍQ��������������߂����܂����B
�@��������ۂł����A���ꂳ�ꂽ���X�̐^���Ŕ��ɂ܂��߂ɕ����悤�Ƃ���Ă���p���Ɋ������܂����B
�@���N�x�A���Z���^�[����͊Ō�Ȃ̐M�{����A��������A�C�c����A���ː��Z�p�Ȃ̋��{����̂S�������ȉ�Ŕ��\���s���܂����B
�@���̔��\���e�y�юQ���҂̔��������ȒP�ɏЉ�܂��B�܂��A�����̎Q���҂͖�1,000�l�A�X��30���̊J���A11���܂Ŋ�u���A11������15���܂ł��e���ȉ�A15������17���܂ŃV���|�W�E�������{���A17��30���ɏI�����܂����B |
|

����u���̗l�q��

�����ȉ�̗l�q��

����u���̗l�q�� |
| �P�D�u �{�ߏƎ˂ɕK������J����Q�\�h�ւ̎��g�݁`��������̊J���P���̓����`�v�ɂ��� |
| �i�Ō�Ȏ�C�@�@�M�{�@���M�j |
�@���q�����{�ߕt�߂ɏƎ˂����ꍇ�̗L�Q���ۂƂ��āu�J����Q�v������A�o���ێ换����b����Ȃǂ̋�ɂ���QOL�̒ቺ�ɂȂ��������Ⴊ�m�F���ꂽ���Ƃ���A���̏�Q���ŏ����ɗ}���邽�߂ɊJ���P���������o�܂ɂ��ďЉ�A�܂��A�P���ɍۂ��Ă͖��H�O�ɂT��J������Ȃǂ̎��{���@��w�����@�ɂ��āA�p���t���b�g�������Ȃ��犳�҂���ɐ����������Ƃ₻�̍ۂɋ�J�������Ƃ��邢�́A���{�������ʂ̔����Ȃǂ���Ȑ������e�ł��B
�@�Q���҂���͊J���P���ɂ��Ă̎��ⓙ������A���^�������s���܂����B
| �Q�D�u ���ÏI����̑O���B���҂̊Ō쑊�k�`�d�b�ɂ�鑊�k���e�̕��͂ƕ]���`�v�ɂ��� |
| �i�Ō�Ȏ�C�@�@�����@�F�q�j |
�@���Z���^�[�Ŏ��ÏI�����҂ɑ��čs���Ă���o�ߊώ@�V�X�e���ɂ��Ă̏Љ�ƁA���̌o�ߊώ@�̈��i�Ƃ��Ă̓d�b�ɂ��u�Ō쑊�k�v�̓��e�₻�̍ۂ̊Ō�t�̖����A���Ҏw���̎��ۂɂ��ĊT���I�ɐ������܂����B
�@���̏�ł���܂ł��Ƃ�̂�����4,000���ȏ�̓d�b���k�������ʂɕ��ނ��A�ł����������u�O���B���ҁv�̑��k���e��ތ^�����A���̕��͂��s������̊��Ҏw���ɖ𗧂Ă�A�ƌ������e�ł��B
�@���Ì�ɂ͂�����҂���ɑ��ď����I�ɋN���肤���Q�ɂ��Ă̐����͍s���Ă��܂����A���̎��_�ŏ�Q���o�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�������o���Ă����Q������邱�Ƃ��������Ƃ��犳�҂���Ɏ������Ȃ��A�\���ȗ����邱�Ƃ�����ł���A���Ò�����ӊ���Q���C���[�W���Ȃ��犳�Ҏw������ƌ����̂��A����̉ۑ�ł���Ƃ̌��_�ł��B
�@�Q���҂���́A���҂��d�b�������Ă��鎞�ԑт͌��܂��Ă���̂��Ȃǂ̎��₪����A���^�������s���܂����B
| �R�D�u ���ː��畆���ɑ���畆�P�A�`�[�������̎��ہv�ɂ��� |
| �i�Ō�Ȏ�C�@�@�C�c�@������j |
�@���q���̏Ǝ˂ɂ��قڑS���҂ɏo������ӊ���Q�Ƃ��āu�畆���v������A���x�͗l�X�ł��邪�A���̗\�h��𑣂��ɂ́A���҂��g�̃Z���t�P�A���������Ȃ��B���̂��ߊ��҂���ɔ畆�P�A�̕K�v���𗝉����Ă��炢�A�މ@����p�������Z���t�P�A���ł���悤�x�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA��t�A�Ō�t�ɂ��u�畆�P�A�`�[���v�����������g�݂ɂ��Đ������܂����B
�@��N�V������̊����̌o�܁A�畆�P�A�`�[���̖����A�X�^�b�t����⌻�݂̎��H�Ȃǂ�������A�܂Ƃ߂Ƃ��ẮA�����̌��ʁA�P�A�`�[�����j�ƂȂ�X�^�b�t�p�p���t���b�g�����p�����X�^�b�t�ւ̋����T�|�[�g���s�����ƂŁA���X�̎����Ō�t�ɑ���P�A��̐Z����A���җp�p���t���b�g�ɂ�芳�҂���̃Z���t�P�A�x���ɂȂ��������A����̉ۑ�Ƃ��āA���҂̃Z���t�P�A�s���̕]����P�A�`�[�������̍X�Ȃ�[�����d�v�ł���ƌ��т܂����B
�@�Q���҂���͏[���̓��e�͋�̓I�ɂǂ̂悤�ɍl���Ă���̂��Ȃǂ̎��₪����A���^�������s���܂����B
| �S�D�u ���q�����Âɂ�����㕠��MRI �����̗L�p���v�ɂ��� |
| �i���ː��Z�p�ȁ@�@���{�@��s�j |
�@���Z���^�[�ł͊̂���̎��Âɓ������ᇂ̐����⎡�Ìv�����̂���EOB�E�v�����r�X�g�Ƃ���MRI���e�܂�p���Č��������{���Ă���Ɛ�������ƂƂ��ɁA���{�ɂ�����̂���̒��ōł������̍זE����ɑ��āA���̑��e�܂͓��ɗD�ꂽ�������\��L���Ă��邱�ƁA����܂ł̑��e�܂ł͂킩��Ȃ������זE����̑����̔����ɂȂ���ƌ����Ă��邱�ƂȂǂ��Љ�܂����B
�@�܂��A���q������ː��ɂ�鎡�Ì�͊̑��ւ̉e���Ƃ��ĕ��ː��̉��������邱�Ƃ�A�ʏ�̕��ː����Âɂ��ẮA��ɋǏ��I�Ȍ����ʂ̕ω����F�߂���Ƃ����͂��邪�A���q�����Âł͏ڍׂȕ��Ȃ����Ƃ���A����A���҂���̋��͂Ăǂ̂悤�ȕω����N�����Ă���̂��ׂ邽�߁A���ÑO�Ǝ��Ì�ɑ��e�܂𓊗^���Ă���MRI �������s���A���̌��ʁA���ۂɗ��q���Ǝ˔͈͂Ɉ�v�����̈悪MRI�����ɂ���ĕ`���o����A���q�����Âɂ��e�����l�����邱�Ƃ\���܂����B
�@�Ō�ɁAMRI�͎�Ɍ`�ԓI�ȏ��邱�Ƃ��ړI�Ƃ���Ă��܂������A����͕����I�ȕ]�����\�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl�����AMRI���g������ʕ]���ɂ��Č������Ă��������ƌ��_�Â��܂����B
�@���^�c�ψ��Ƃ��ĎQ�����A�c���̌��������A����������[���x���܂ő�ςȈ���ł������A�u����̒B�����v�𖡂키���Ƃ��ł��A���ɗL�Ӌ`�Ȋw��ł������Ǝv���܂��B
�Ǝˊ��Ԓ��̖����̂ЂƂƂ�
�Ō��
���q����ÃZ���^�[�́A��l�ЂƂ�̊��҂���̕a�C�Ɍ���������p���d������Â�W�J���Ă��܂��B�Ō�t�͊F����̈ӎu����v���Z�X�𗝉�����ƂƂ��ɁA�L�Q���ۂ���̋�ɂ��ŏ����ɂł���悤�S�g�̃T�|�[�g���s���Ă��܂��B
�g�@�����b��h
���҂��g���[�������������Â̒�
�@���Z���^�[�ł́A���q�����Â����銳�҂����ΏۂɁA���Q��u�@�����b��v���J�Â��Ă��܂��B�H��@���ɂ��u�b�g���q�����Â⎡�Ê��Ԓ��̋C�����̂���悤�h�⊳�ғ��m�̌�荇���ƊŌ�t�̏��������S�ł��B
�@���̂��Ƃɂ��A�ߓx�ȋْ����ق���A���Âɗ����������E�C�������ƂɌq�����Ă��܂��B���҂��m�A���Â����Ɍ𗬉�̏����A�D�]�ł��B�S��������̕��A�����x���Q���������B
|
|

�i�g21�N�W���@�����b��j�����Ȏ��^���� |
�g�~�j�R���T�[�g�h
�����̉��y��œ��a�ӗ~���T�|�[�g���܂�
�@���q���Ǝˊ��Ԃ͕a�C���ʂɂ���Ă��l�X�ł��B�Z���ꍇ�͖�10���A�O���B�����̑�����E�X����͂P�`�Q�����v���܂��B���̂��߁A���ύ݉@������31���ƒ����Ȃ�܂��B���Ấu�̂ɂ₳��������p�̂Ȃ����Áv�Ƃ����C���[�W������܂��B�������A���ۂ͏Ǝ˂ɂ��畆���E���o���ȂǗL�Q���ۂւ̑Ή��₻��ɔ����S�g�̕��S������܂��B���Â��p�����邽�߂ɁA�S�Ƒ̂̃G�l���M�[�𑽂���₵�܂��B�������́A���Ɋ��҂���̃I�A�V�X�ƂȂ�Ȃ���A�����Ȏ��Ð��s��ڎw���`�[����Â̐��i�Ɩ����̎��Ԃ���Ă��܂��B
|
 |
�iH21�N�U���j
�_�˂̏����U�l�R�[���X
�O���[�v�g��D�h�ɂ��
�A�J�y���R���T�[�g |
 |
�iH21�N�X���j
���҂̉��l�ɂ��g���̓J�h
�~�j�R���T�[�g
|
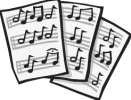 |
�������������҂����
�g������ɖ����̃V���t�H�j�[�h��
�t�ł܂� |
|
���q����ÃZ���^�[�ɕ��C�����`�l�Ƃ̂Ȃ���`
���ː��Ȉ㒷�@���n�@���K
�@���̂S�����瓖�Z���^�[�ɕ��C���Ă��܂��B�ȑO�͍����a�@�@�\�̐_�ˈ�ÃZ���^�[�i�_�ˎs�{����j�ŁA���ː��ȋƖ���ʂ��s���Ă��܂������A���ː����Âɂ͏T�ɂP�����x�]�����Ă��܂����B
�@���̂��сA���Z���^�[�ɍ̗p����A���ː����Â̌o����ς݁A�����A���ː���ᇈ�Ƃ��āA���ÂɌg����Ă�������ƍl���Ă��܂��B
�@���q���Ƃ�������ȕ������������������ː����g�p���鎡�Â�ڂ̂�����ɂ��āA����ɐN����ꂵ��ł��銳�҂���ɑ��āA�Ő�[�̋@����g�p���A��ËZ�p����g���āA�����ǂ����鎡�ÂƂ��Ċ����ƂƂ��ɁA���͂������Ă���܂��B
�@���܂ň�ÂɌg����Ă��āA�������������Ƃ́A�u�l�Ƃ̂Ȃ���v����Ƃ������Ƃł��B���҂���ɂ��\���Ȑ������s���A�����Ɣ[�������Ē����A�ǂ��R�~���j�P�[�V�������Ƃ�āA�M���W��z�����Ƃ����Âɔ��ɏd�v�ƍl���܂��B���҂���̋��͂Ȃ����āA���Â𐋍s���邱�Ƃ⎡�Â̌��ʂ��]�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�@�܂��A���Â̓`�[����Âł��B���͂̃X�^�b�t�A���Ȃ킿��t�A�Z�t�A�Ō�t�A��t�A�����Ɩ��ɘA�g���Ƃ�A��̎��Ái�����ǂ����邱�Ɓj���s�����Ƃ��ł��܂��B���̉ߒ��ł��ǂ����Ö@��͍����邱�Ƃ⊳�҂���̕a�Ԃ��f������A���Ìv��̏C���A����̂��Ƃɂ��Ęb����������A���҂���̊��𐮂��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B���̍ہA���͂̃X�^�b�t�Ɨǂ��W��z���Ă���Ɣ��ɃX���[�Y�����̂��Ƃ��s�����Ƃ��ł��܂��B
�@������A�u�l�Ƃ̂Ȃ���v���ɂ��Ȃ���A���q�����Â̔��W�Ɋ撣���čs������ƍl���Ă��܂��B
���������H�ׂ���悤��
�Ǘ��h�{�m�@����@���q
�@���͂��̂X������蓖�Z���^�[�ɉh�{�m�Ƃ��ċΖ����Ă��܂��B�ȑO�͎Љ���{�݂ɋΖ����Ă���a�@�ł̋Ɩ��͏��߂ĂɂȂ�܂��B
�@�Ζ����Ă����A�ێ�ʂ��ቺ���Ă������҂���𑽂���������悤�ɂȂ�܂����B�ȑO�A�Ζ����Ă������ł��悭����������i�ł����B�����ł���������H�ׂĂ��炢�����Ƃ�����S�Ō��������Ă��܂����B�P�l���A�u�H�ׂ����Ȃ��v�u�H�ׂ��Ȃ��v�Ƃ��������͈Ⴂ�܂��B���̓s�x��������K�₵�A���b���܂����B�����Ă��̉�b�̒����猴���������o���A�H���`�Ԃ̕ύX�A�Ƃ�ݍ܂̎g�p�A�����ĐH�ׂ����Ǝv�����̒Ȃǂ��܂��܂Ȏ��g�݂��s���܂����B
�@���̌��ʁA�u�����Ȃ�H�ׂ�ꂽ�v�u�~�L�T�[�H�ɂ���ƐH�ׂ�ꂽ�v�Ƃ��������悤�ɂȂ�܂����B���̎��͊��҂����莄�̕������ꂵ��������������܂���B���̌�̂����X�Ɍ��C�ɂȂ�ADL�����サ�Ă����܂����B�H���ɑS����K�v������������̕����X�v�[���������Ď��͐ێ悪�ł���܂łɉ����Ƃ��ɂ͑S�E���Ŋ�̂�N���Ɋo���Ă��܂��B
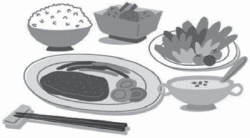 �@��������������H�ׂ邱�Ƃ͌��C�Ȑl�ɂ͓�����O�̂��Ƃł����A���҂���ɂƂ��Ă͓�����ƂɂȂ�ꍇ����������܂��B�H�ׂ邱�Ƃ���ɂɊ����ߊϓI�ɂ����Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���͖��������ł��B���җl�̏�Ԃ������Ȃ���A�����ł����������H�ׂ�����@�𑼐E��̕��̋��͂Ȃ���A�h�{�m�Ƃ��Đ���t�T�|�[�g���Ă��������Ǝv���܂��B �@��������������H�ׂ邱�Ƃ͌��C�Ȑl�ɂ͓�����O�̂��Ƃł����A���҂���ɂƂ��Ă͓�����ƂɂȂ�ꍇ����������܂��B�H�ׂ邱�Ƃ���ɂɊ����ߊϓI�ɂ����Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���͖��������ł��B���җl�̏�Ԃ������Ȃ���A�����ł����������H�ׂ�����@�𑼐E��̕��̋��͂Ȃ���A�h�{�m�Ƃ��Đ���t�T�|�[�g���Ă��������Ǝv���܂��B
���Ɍ������q����ÃZ���^�[�Ō��C����
��������w�@�L���@��
�@���ɂɌ��C�ɗ��Ă��瑁�P�N���߂��܂����B�v���Ԃ��A���ɂ����Ƃ����Ԃ������Ɗ����Ă��܂��B�������A���ɂƂ��Ă͌����̂P�N�ł���A���������̂Ȃ��M�d�ȂP�N�������ƍl���Ă��܂��B���ʂ���āA���w���������������̐搶����X�^�b�t�̕��X�ɐS��肨���\���グ�܂��B
�@�����́A��������w�̈���Ƃ��āA�w�h�Ɍ��ݗ\��̗��q�����Î{�݁u���f�B�|���X�v�𑤖ʂ���T�|�[�g����ړI�ł̌��C�ł���܂������A�C���t���A���̊Ԃɂ����f�B�|���X�̗����グ�ɑS�͂��X���鎩�������܂����B����͂��̌��C�ŁA���q�����Â̏d�v����g�ɂ��݂Ċ���������ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@���Ɍ������q����ÃZ���^�[�͑����̓_�ŁA����܂ł̕a�@�̊T�O��傫�������܂����B�a�@�̗��n�A�v�A�V�X�e�������ꂽ�J���e�⎡�Ê��҂̏��Ǘ��Ȃǂ����̗�ł��B��^�{�݂�K�v�Ƃ��A�܂����҂ɑ��Ă͔�r�I��Q�̏��Ȃ����q�����Î{�݂Ȃ�ł͂̒��z�ł����A������\�N���O�ɁA���̂悤�ȍ\�z�����A�����������̎{�݂Ƃ��Ă�����������A���������Ă���挩���Ə�M�ɂ����A���͍ő�̌h�ӂ������Ǝv���܂��B
�@���q����X���ɂȂ�����������L���A���זE�E�����ʂ������A���ɐ��n��������X�����Âɔ�ׁA���q�����Â̐L�т���͔��ɑ傫���A����v�X���W���Ă������̂Ǝv���܂��B�ԂŗႦ��Ȃ�A���̗��q�����Ấe�炫�n�߁f�ł��傤���BX�����Â͑����e���J�f�ɍ炫�ւ��Ă��܂����A���̂������q�����ÂɎ���đ�����\�������蓾�Ȃ��b�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@���́A��������w�ɖ߂�A���ː����Â��s���T��A�w���𒆐S�ɗ��q�����Â̂��炵���A�\������X�����Ă��܂��B�����g���A���N�̏t�ɂ̓��f�B�|���X�̗����グ�ɖ{�i�I�ɎQ������\��ł��B����́A���Ɍ������q����ÃZ���^�[�̑��Ɛ��Ƃ��Ă̌ւ�����ɁA���q�����Â̍X�Ȃ锭�W�ɁA�䂪�g����������Ǝv���Ă��܂��B
��Ãg�s�b�N�X
�@���c�@�l�Ђ傤���Ȋw�Z�p����ł́A���ɂɂ�����Ȋw�Z�p�̐U����ʂ��āA���������̌���ƒn��Љ�̊������ɍv�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�����S�N�V������A�����ɍ܂��͍ݏZ���錤���҂�ΏۂɁA���R�Ȋw����ɑ�����e��̌������������{���Ă��܂��B
�@���̓x�A���Z���^�[���ː��Ȃ̏o���㒷�i���ː���ᇊw�E���q�����Êw�j�̌����e�[�}���A����21�N�x�����������ƂƂ��č̑�����܂����B
| �����e�[�} |
���q�����Ê��Ҍ��̂̈�`�q��͂ɂ��e�[�����C�h���Â̊m��
|
| ���̔w�i�ƈӋ` |
���q�����Ái�z�q���E�Y�f���j���҂̌��̂���`�q��͂��A��`�q�����Ǝ��Â̌��ʁE����p�Ƃ̑��֊W�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ��A���ÑO�ɗ��q�����Â̌��ʁE����p��\�����čőP�̎��Ö@�I�����s���e�[�����C�h���Â̊m����ڎw���B |
|
|

