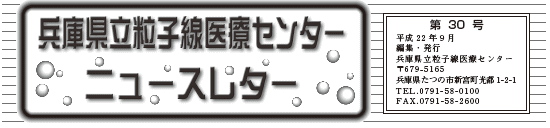
CONTENTS
�����@�@���A�C�̂����A
�����@���Ɍ������q����ÃZ���^�[�ɂ����闱�q�����Â̌���
�����@�����e�J����
�����@���Ɍ������q����ÃZ���^�[�Ŋw����
�����@���q����ÃZ���^�[�Ζ���U��Ԃ�
�����@H21�N�x�̗��q����ÃZ���^�[�̊Ō�Ȃ̕��݂Ɩ����\�z�}�I
�����@��Ãg�s�b�N�X ��p�s�\�X������ɑ���R����ܕ��p���q������
�@����22 �N�S����蕺�Ɍ������q����ÃZ���^�[�̉@���ɏA�C�������܂������㏹�Y�ł��B�J��10 �N�ڂ̂���Ȃ锭�W�����߂��鎞���ɉ@���̐E��������A�E�ӂ̏d���ɐg�̈������܂�v���ł������܂��B���݂܂ŁA�����̊��҂���Ɏ��Â��Ă����������Ƃ��ł��܂������Ƃ́A�֘A��Ë@�ւ̊F�l����̂��x���ƃX�^�b�t�ꓯ�̂���܂ʌ��r�̎����ł���Ɗ��ӂ������Ă���܂��B���ꂩ����S�͂Őf�ÁA������簐i���鏊���ł��B
�@���Z���^�[�͕���13 �N�ɗz�q���ƒY�f���̂Q��ނ̗��q�����Â��s���鐢�E�B��̎{�݂Ƃ��ĊJ�݂���A����܂�3,200 �����銳�҂���̎��Â����{���Ă܂���܂����B���q�����ẤA�̓��ɂł�����ᇂ̏ꏊ�ŗ��q�����~�߂č����ʓ��^���ł��A�������ʂ��Ǝ˂��Ă��]���̕��ː���肪��̎E���\�͂������Ƃ�������������܂��B���̓�������肭���p���邱�ƂŁA���A�x�A�́A�O���B�A����Ȃǂ̑��킩�甭��������ᇂ�p���ŏ����ɗ}���Ȃ��玡�����Ƃ��ł��܂��B
���͉��L��M���Ƃ���Â��s���Ă܂���܂��B
�P�D������
�@�痘�x�́w�������ďo����Ă��邱�̎��Ԃ́A��x�Ə����Ă͗��Ȃ���������x����̂��́A���̈�u���Ɏv���A���o����ō��̂����ĂȂ������܂��傤�x�Ƃ������_�ł��B���҂���A���@���ꂽ�S�Ă̕��X�Ɉ�����̊o��Őڂ��Ă��������Ǝv���Ă���܂��B
�Q�D���Ғ��S�̗��q������
�@���q�����Â̗D�ꂽ�������ő���Ɋ������A���Â�����S�Ă̊��҂���Ɉ��S�ł��������Ă��������鎡�Â�������܂��B�X�^�b�t�ꓯ�A���҂����l��l�̗���ɗ�������ÁA���Ȃ킿�u���Ғ��S�̃`�[����Áv��O�ꂵ�čs���Ă䂭�����ł��B
�R�D���q�����Â̕��y
�@���q�����ẤA��r�I�����Ȃ���ɑ��Ă͐炸�Ɏ������Ƃ��ł��A�ŋ߂ł́A���Ȃ�i�s��������̐�����ڎw�������g�݂��i�݂���܂��B���̂悤�ɗL���Ȏ��Ö@�ł���ɂ�������炸�A���݁A�䂪���ɂ����闱�q�����Ñ��u�͂킸���W�䂵������܂���i�]���̕��ː����Ñ��u�͖�800 ��j�B���Ìo������A�]���ł͍���ł������Ǐ�ɘa���܂߁A�����̊��҂�����~�����Ƃ��ł���Ɗm�M���Ă���A���u�̒ቿ�i���A�Z�p�͂̍��x���A�Տ������̎��{�A���Ð��ʂ̔��M�A�����ÂƂ̋����A��b�����A�l�ވ琬�Ȃǂ��[�������A���q�����Â��L�����y�����邽�߂ɐs�͂��Ă䂫�����ƍl���Ă��܂��B
���N�x�̖ڕW
�P�D��葽���̊��҂���ɗ��q�����Â�
�@�K�������̊g��A�Ƃ��ɂw�����ÂƂ̕��p���Ái�u�[�X�g���Áj�̊J����O������̎��Â̈˗�������������A�����̑���������ł��B�o�c�ʂł��A���N�x�͏��̒P�N�x��������B���������ƍl���Ă��܂��B
�Q�D���q�����Ð��т̍X�Ȃ����
�@�ߋ��̎��Ì��ʂ�T�d�ɕ��͂��āA���Ð��т�K���ɕ]�����A�K�v�ɉ����Ď��Ê�̌�������}��A���Ð��т̍X�Ȃ�����ڎw���Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�R�D���Ë@�\�̏[��
�@�j��ؑ֎��Ԃ̒Z�k���ɂ�闘���̌���A���тɎ��Ñ��u�������Ԓ�~����s���̎��Ԃ�z�肵�āA���̗��q�����Î{�݂Ƃ̘A�g�����Ă��܂��B
�S�D�a�@�@�\�̏[��
�@�a�@�J��10 �N�ڂ��}���A���H�̏[���A�z�[���y�[�W�̉��P�A���҂���p�̕a�@������LAN ���A�a�@����̔����@���A���҃T�[�r�X�̌���Ɍ��������g�݂��l���Ă��܂��B����Ɉ�È��S�̂���Ȃ鋭���𐄐i���Ă����܂��B
�T�D���q����Â̌����ʂ̏[��
�@�z�q���ƒY�f�����Â̗Տ������A���̗��q�����Î{�݂�A���̐f�ÉȂƂ̃R���{���[�V������ʂ��AQOL �̍����V�������Ö@�̊m����ڎw���Ă��܂��B�܂��_�ˑ�w�����w�Ƃ̘A�g��w�@�Ƃ��Ă̊����A�Ɨ��s���@�l����Ռ������A�Ɨ��s���@�l���{���q�͊J���@�\�Ƃ̘A�g�ŁA���q�����Â𒆐S�Ƃ�����b�����ɂ��͂����Ă��܂��B���̂��ߑ�U���ڂ̊J���Ǝˎ��̐������������܂��B
�P�D���Î��сi2010 �N�R�������_�j
�@���Z���^�[�ł́A2003 �N�S���̈�ʐf�ÊJ�n����2010�N�R���܂ł̂V�N�Ԃ�3,215 ���̊��҂���Ɏ��Â��s���Ă��܂����B
�P�j��\�I�Ȏ����̌X���ƌ���
�@������
�@2008 �N�x�܂ł͉E���オ��ł������A2009 �N�x�ɂ�⌸�����܂����B�������A����ł���R�ʂł���A���q�����Â̓K���ƂȂ��\�I�����ł��邱�Ƃɕς�肠��܂���B�g�D�^�ʂł́A�G����炪��A�������F��A�B�l�X�E���O��g�D�^�ŁA�S�̂̂V���ȏ���߂܂��B���ɁA�������̑�\��X �����Â�R������Â������ɂ����������F��A�B�l�X�E����ɂ��ẮA�S���ł��L���̊��Ґ������Â��Ă���A�Q�N�Ǐ����䗦�͂������80���ȏ�ƗǍD�Ȍ��ʂ��o�Ă��܂��B
�A�x����
�@�������ł͂���܂����A�����X���ɂ���A2005 �N�x�ȍ~�͑�S�ʂƂȂ��Ă��܂��BI �������X ���ł̒�ʕ��ː����Â��ی��K���ƂȂ��Ă���܂��̂ŁA�������I�Ԋ��҂���������Ă��Ă���Ǝv���܂����A��ᇌa���Rcm ����T�Q�͗��q�����Â̕����ǂ��Ƃ����f�[�^����������A�܂��A�d�Ăȕ��ː��x���͗��q�����Â̕������Ȃ��Ƃ����f�[�^���o�Ă��܂��B����ɁA���Z���^�[�ł͋��ǐZ���Ȃǂ�T�R���ϋɓI�Ɏ��Â��Ă��܂��B
�B�̂���
�@�ߔN�A���Ґ��̑������������A2008 �N�x�����Q�ʂƂȂ��Ă��܂��B�E�C���X�������̉���̍d�ς��x�[�X�Ƃ���̍זE���قƂ�ǂ��߂܂����A���x�����o�Ă��邱�Ƃ������̂ŁA������̎��Â���ꂽ���҂������̂������ł��B��x�Ǝ˂������ʂ̂����߂��ɍĔ������ꍇ�A�ďƎ˂͔��ɐT�d�ɂȂ炴��܂��A����܂ł̂Ƃ���A�K���ɂ��čďƎ˂ɔ����d�Ăȕ���p�������������҂���͂����܂���B
�C�X����
�@2007�N�x�܂ł͍��v�ł�24���ł������A2008�N�x�ɉ��_�Q���V�^�r�������p����Տ��������J�n���Ă���̑����͂����܂����A2009�N�x��55���Ƒ�T�ʂɖ��o�܂����B�ڂ����́A�{���Ɏ����㒷���������L�����f�ڂ���Ă��܂��̂ŁA����������Q�Ƃ��������B
�D�O���B����
�@��ʐf�ÊJ�n�ȗ��A��т��đ�P�ʂŁA����܂�1,200���ȏ�����Â��Ă��܂������A���Ì��ʁE����p�Ƃ����҂��ꂽ�ʂ�̗D�ꂽ���ʂ������Ă��܂��B���݁A�i�s���̊��҂���ɑ�����ʑ������������ł��B
�E������
�@����ƌĂ����������ᇂ̑�\�ł��B�H�Ȏ����ł����A���q�����ÈȊO�ɗL���Ȏ��Ö@���Ȃ��ꍇ�������A�S�����犳�҂��W�܂��Ă��܂��B�ߔN�͔N��20 �` 30���Ő��ڂ��Ă���A��U�ʂƂȂ��Ă��܂��B�g�D�^�ʂł́A�ҍ���A�������ې��g�D����A������A�����A���b����Ȃǂ������Ȃ��Ă��܂��B
�N�x�ʎ����ʓ���
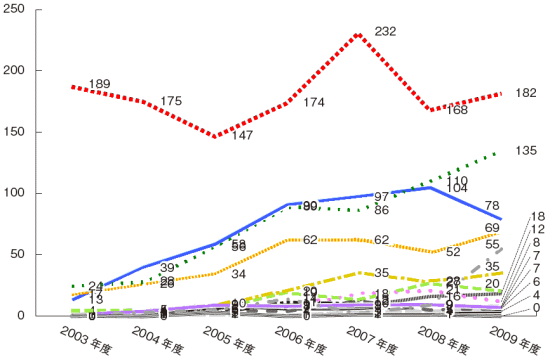
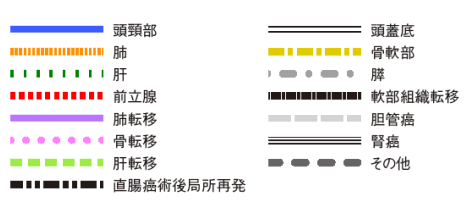 |
�Q�j���҂��Z�n��̕ω�
�@��͂�n���E���Ɍ��ݏZ�̊��҂���ԑ����̂ł����A�������E���オ��ɂ��ւ�炸�A�����ŁA�S�̂ɐ�߂銄���͌����X���ł��B����́A���̋ߋE���܂߂��ߋE�n���S�̂ɂ������邱�Ƃł��B
�@�֓��n���Ȗk�́A��t���E��錧�E�������ɗ��q�����Î{�݂����邱�Ƃ�����i���N�A�Q�n���ɂ��ł��܂����j�A���܂�Љ����܂��A�ߋE�n���Ȑ��͓��Z���^�[���B��̗��q�����Î{�݂ł��̂ŁA���q�����Â̒m���x���オ��ɂ�A�����E�l���E��B�n���̊��҂���̏Љ�����Ă��Ă��܂��B���ɗ��q�����Î{�݂̂��钆���E�k���n���̊��҂���������X���ł����A����͎�Ƃ��Ĉ��m������̊��҂���ŁA���É��s�ɗz�q�����Î{���݂̗\�肪����A�����̒��ړx����������Ǝv���܂��B
�@���A�C�O����̊��҂���i�C�O�ݏZ���{�l�͏����j�́A2009 �N�x�܂łł킸���R���i�؍��Q���A�����P���j�ł������A2010 �N�x�ɂȂ��Ċ��ɂS�����Â��܂����i2010�N�W�����݁j�B����ɂ��ẮA�����ŏڂ����q�ׂ܂��B
�Q�D�C�O����̊��҂���̎���ɂ���
�@�ŋ߁A�g��Ãc�[���Y���h�Ƃ������t���ɂ킩�ɋr���𗁂тĂ��܂����A����́A���{�̍��x�Ȉ�Â��C�O�̕x�T�w�ɒ��邱�ƂŁA��Â�o�ς̊�������}�낤�Ƃ�����̂ŁA�o�ώY�ƏȂ�ό����������s��Ƃ��Ē��ڂ��Ă��܂��B
�@���Z���^�[�͂��̂悤�Ȋ�����ϋɓI�ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł����i�p��ł̃z�[���y�[�W�����邾���ł��j�A���{�̍Ő�[��Â̑�\�ł��闱�q�����Â͊C�O��������ڂ������悤�ŁA�C�O����̖₢���킹�i�d�b�EFAX�E�d�q���[���j���p�ɂɂ���܂��B�قƂ�ǂ͏�����œ��Z���^�[��f�ɂ͎���Ȃ��̂ł����i���i�s�������Ă��āA���q�����Â̓K���ɂȂ�Ȃ��ꍇ�������j�A���N�x�ɂȂ��Ċ��ɂS���̊��҂���̎��Â��I�����܂����B���҂���̋��Z���́A�����A�؍��A��p�A�^�C�ł��B���N�̂V�`�W���ɂ͂��̂S���������Ɏ��Â��Ă�������������A���̉Ƒ��E�F�l�ȂǑ����̊O���̕����O���E�a���Ō������܂����B
�@���������̈�Â��C�O����������]������Ă���Ƃ�����т��������ŁA�����J�͓͂��{�l���҂���̉��{�ɂ��Ȃ�܂��B�f�@���͊�{�I�ɒʖ������肢���Ă���̂ł����A��p�̖�肪����̂�����Ă��炦�Ȃ����Ƃ������A�p���b�����t���Ή����邱�ƂɂȂ�i���҂��͖{�l�܂��͉Ƒ����p���b���邱�Ƃ��قƂ�ǂł��j�A���̈�t�̕��S�������܂��B�܂��A�ʖ��Ă��A�����ɂ����鎞�Ԃ͔{�ȏ�ɂȂ�܂����A���������܂��`��炸�A���҂�������Ă����P�[�X������܂����B����ɁA���{�l���҂���ɂ̓��[�`���ōs���Ă���P�A���s���Ă��Ȃ��������Ƃ�����A���҂���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����s���������ł������Ǝv���܂��B
�@����A�O���l���҂���̎��ꂪ��������̂͊ԈႢ����܂���̂ŁA��C�X�^�b�t�i�p���b���āA��Âɐ��ʂ��Ă���l�ށj�̔z�u���v����i�p��A������A�؍��ꂠ���肩�j�ŏ����ꂽ���������̍쐬�ȂǁA����̐��𐮂��Ă����K�v������ƍl���Ă��܂��B
�@���u�Ǘ��Ȃɂ͕������U���Ă����E�����z������Ă��܂��B�ȑO�͈�ÂƂ͖��W�̂Ƃ���ɂ����l�ŁA���q�j��f���q�̕����w�ɂ��Č������Ă��܂����B���ꂪ�����̉��ŗ��q�����Âɏo��A��w�Ɍg���悤�ɂȂ�܂����B���q�����Â͌��q�j��f���q���g�������ː����Âł���A���܂ł̌����œ����m����l�̂��߂ɖ𗧂Ă邱�Ƃ��o�����̂ł��B
�@�������͊��҂���Ƃ��܂�ڐG���邱�Ƃ͂���܂��A�����Ƃ��ē��X�����Ă��܂��B���q�����Âɂ́A����ȁg������h�Ƃ������u���K�v�ł��B������Ƃ����͈̂�ʂɖڂɂ���悤�ȑ��u�ł͂���܂��A���q�j�E�f���q���������Ă���l�X�ɂƂ��Ă͉�������g���Ď������s���̂Őg�߂ȑ��݂ł��B���̊Ǘ����A���[�U�[�ł���f�Õ��ː��Z�t��u�̃I�y���[�^�ł���O�H�d�@�̉^�]�Z�p����Ƌ��͂��čs���Ă��܂��B
�@�܂��A���҂���ɂǂ̂悤�ɗ��q�����Ǝ˂��邩�Ƃ����Ƃ���ł́ACT �摜���g�����v�Z�@�ɂ��͋[�I�Ȏ��Ái���Ìv��j���s���Č��߂܂��B���ۂɊ��҂���ɏƎ˂��Ē��ׂ�킯�ɂ͂����Ȃ�����ł��B���Ìv����s�����u���������v�Z�̊m���炵���ׂ��肷�邽�߂ɂ́A���q���̕��������łȂ��v�Z�@��v���O���~���O�Ȃǂ̒m�����K�v�ƂȂ�܂��B���̒m�����g���Ď��Ìv����쐬������A�ԈႢ�Ȃ��v�悪�쐬����Ă��邩�ǂ������`�F�b�N�����肵�Ă��܂��B
�@�ȏ�A���u�Ǘ��Ȃ̊ȒP�ȏЉ�ł����B�Ƃ���ŕ\��Ƒ��u�Ǘ��Ȃɂǂ�ȂȂ��肪����̂ł��傤���B��́A�����e�J�����Ƃ́c�B
�@�����e�J�����i�@�j�Ƃ͐��w�E�����w�I�v�Z��@�̈�ł��B1940 �N��̔����A�m�C�}���ƃE�����ɂ���Ē�Ă���܂����B�ȒP�ɂ����Ɨ�����p���Ė����������@�̂��Ƃł��B�ŋ߂ł͐��l�I�E�����I���f�����x�[�X�ɗ������g���ă��f���������s�����Ƃ��w���܂��B���O�͂܂��ɁA�q���J�W�m�ŗL���ȃ��i�R�����̂S�̒n��̂P�A�����e�J�����ɗR�����Ă��܂��B
�@�������͂��̃����e�J�����@���g���āA���q�����Ẫ��f���������s���Ă��܂��B�O�Ɍv�Z�@�ɂ��͋[�I�Ȏ��Â��s���Ə����܂������A����܂Ŏg�p���Ă����]���̌v�Z�@�ł͌v�Z���Ԃ̖�肩��A���ȑf�����ꂽ���@���g�p���܂��B���̌v�Z���@�ł͂T�b���x�Ōv�Z���I���邱�Ƃ��o���܂��B���̏]���̕��@�͌v�Z���Ԃ�ߖ邽�߂ɂ��낢��ȉ�����܂�ł��܂��B���̂��߁A�{���ɐ������Ǝ˂��v�Z�ł��Ă���̂��A�Ƃ����s��������܂����B
�@����A�����e�J�����@�ł͗��q���P���ǂ��Ă����l�̓��ł̕����v���Z�X�J�Ɍv�Z���܂��B���Âł�10��10����x�̗��q�����҂���ɏƎ˂���킯�ł����A�����e�J�����@�ł͂���10 ���̂P���x�A10 �̂X����x�̗��q�̋O�Ղ��v�Z�@�̒��Œǂ��Ă����܂��B���̂��߁A�v�Z�̐��x�͔��ɍ����̂ł����v�Z���Ԃ��c��ŁA���X�̎��ÂɎg�p���邱�Ƃ��ł��܂���B�ȑO�́i���Ǝd�����Řb��ƂȂ����j�X�[�p�[�R���s���[�^�ł������������Ă����v�Z�ł����A�悤�₭�ŋ߁A����̃p�[�\�i���R���s���[�^���g���Đ����Ōv�Z���I���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��ė��܂����i����ł��܂������I�j�B�܂��A���q�������������e�J�����@�̃v���O�����R�[�h����������Ă��܂����B�����Ŏ������́A�����e�J�����@�Ŋȑf�����ꂽ�v�Z���@���`�F�b�N���Ė��̂Ȃ����Ƃ��m�F���悤�Ƃ��Ă��܂��B�}�͂��̂P��ł��B���銳�҂����CT �摜�����肵�ă����e�J�����@�Ōv�Z���Ă݂܂����B���̊��҂����I�̂́A�l�̂̒��ōł����G�ȁi��C�⍜�A��g�D������g��ł���j���ʂŏd�v�ȑ���i�Ґ���_�o�Ȃǁj���������݂��邽�߂ł��B�]���@�ƃ����e�J�����@�ɂ��v�Z���ʂ��r�����Ƃ���A���Õ��j��傫���ς���قǂ̑傫�ȈႢ�������邱�Ƃ���܂���ł����B�܂萳�����Ǝ˂��v�Z�ł��Ă��邱�Ƃ��m�F�ł��܂����B���ꂩ��͑��̕��ʂɂ��Ă��m�F���s���Ƃ���ł��B
�@���̂悤�Ɏ������͕����w�I���n���痱�q�����Â̐��x�������Ă��܂��B�����Ċ��҂��m���Ɉ��S���Ď��Â��邱�Ƃ��o����悤�w�͂��Ă��܂��B
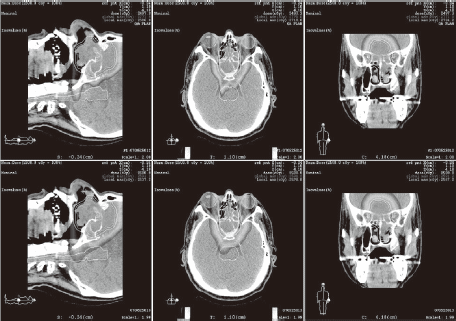
| �}�F �オ�����e�J�����@�ɂ��Ǝ˃V�~�����[�V�����A�����]���@�ɂ��Ǝ˃V�~�����[�V�����B�قƂ�LjႢ�������Ȃ����Ƃ��m�F�ł����B |
|
�@1994 �N�A�_�ˑ�w��w�����ː��Ȗ��_�����̖ؑ��C���搶����ˑR�d�b������܂����B�����A���͕��Ɉ�ȑ�w���ː��Ȃōu�t�����Ă���A���ː����Â̐ӔC�҂Ƃ��ċΖ����Ă����̂ł����A���Ɍ��ŐV�������q�����Î{�݂����̂ŁA��t�Ƃ��ĎQ�����Ȃ����Ƃ����ؑ��搶����̂��U���ł����B
�@���́A�_�ˑ�w��1974 �N�ɑ��Ƃ��܂������A�J�ƈ�ł��镃�̌���p�����ƍl���Ă���A�Ƃ���߂��āA���ː��ȏ������̏]�Z�킩��U���������Ƃ�����A���Ɉ�ȑ�w�Ō��C�����邱�Ƃɂ��܂����B�����̕��Ɉ�ȑ�w�́A�ł�������ŁA�M�S�Ȑ搶�������A���ː����Â���傩��A���̌㍑������Z���^�[�����a�@�����ɂȂ�ꂽ�r�c�搶���T�ɂQ���Ă���A�r�c�搶�ɏo��������ƂŁA�J�Ƃ���߂ĕ��ː����È�Ƃ��Ă̓�����ނ��ƂɂȂ�܂����B�r�c�搶�ɂ����߂����ɂQ�N�ԏT�Q����ː����Â��w�тɍs���܂������A���̌�́A�_�ˑ�w��w�����ː��Ȃ��獡��搶�i���A����ÒZ����w�w���j���T�Q�Ɉ�ȑ�w�ɗ����Ă������Ƃ�����A���낢�닳���Ă��������܂����B
�@�Տ����痣��邱�Ƃ�S�z���Ă����A���Ɉ�ȑ�w�̋����⓯����t���������܂������A�����̐ӔC�ł���̂Ȃ�A�S�������Ȃ����e�Ɉ�Ă�ꂽ���Ƃ��������̂ł��傤���A�ؑ��搶����̗U����������l�ōl�������邱�Ƃɂ��܂����B
�@�����̏������ɓ���܂������A�������Ƃ��Ă̑S���̑f�l�ł��鎄���A�Γc�Q����������w�����Ă������������Ƃ��A���Ŋw�ŏ��ł��B��w�́A�l�l�̌��������W�c�ł����A���́A�g�D�ł��B�g�D�̂�������������m�邱�Ƃ��ł��܂������A��w�̗ǂ��ʂƌ��̗ǂ��ʂ��������ƍl���Ă����̂ł����A���q����ÃZ���^�[�̉@���Ƃ��āA�����͎����ł����C�����܂��B���s��w��w�����ː��ȋ����A�������s�a�@�̉@�����C���ꂽ�������K�搶�Ɍ��ɌĂ�ł���ꂽ�̂́A�ؑ��搶�̂��l���ł����B�ؑ��搶�́A�����w������ɂ͔N��I�ɂ���ǂ��̂ň����搶���N�̎w���̂��߂Ɍ��ɗ��Ă����������̂��Ə�X����������Ă��܂����B�����搶����́A��t�Ƃ��Ă̂�����A�����҂Ƃ��Ă̂�����A�@���Ƃ��Ă̂�����ȂǑ����̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B
�@���Ɍ��Ɏ����̂ōŏ��̗��q�����Î{�݂����̂����f���ꂽ�̂́A�L���O�m���ł��B�m���́A�d���Ȋw�����s�s�ł̗��q�����Î{�݂����߂܂������A�������̐��Ƃł��镨���m���t�Ɋւ��ẮA���ƂƂ��Ă̊����������Ă��������Ă��܂����̂ŁA���́A�����搶�Ƃ����k���Ȃ���A�a�@�炵���Ȃ��a�@�����ׂ��F�X�i�āj���l���܂������A���ꂪ�����ł����̂͏������̎����E���̋��͂�����������ł��B
�@�u��ÂƂ��Ă̗��q�����Â�����v���Ƃ�m�����猾��ꂽ�̂ł����A��ÂƂ͉������l���A�p���ł���Ƃ������_�Ɏ���܂����B�a�@������Ă��Ԃ�Ă��܂��Ă͑ʖڂȂ킯�ł��B�p�����邽�߂̃|�C���g�͂Q�ł��B�l�ƌo�c�ł��B�a�@�����t�����Ȃ��Ȃ�Όp���ł��܂���B�ǂ̂悤�ɗǂ��a�@�ł����N�Ԏ��������A������p���ł��Ȃ��Ȃ�܂��B��t�����肳���邽�߂ɂ́A�_�ˑ�w��w���̃o�b�N�A�b�v���ǂ����Ă��K�v�ƍl���܂������A���̂悤�ȕ�Z���ŏ������яo�������̂ɂ́A����͌��\��ςȂ��Ƃł��B�����̐_�ˑ�w�w���́A��w������̐��ˑה��搶�ł����̂ŁA���k�Ɏf���A�A�g��w�@�ɂ��Ă��������܂����B������w���n�������̂̈�a�@�ƘA�g����悤�Ȃ��Ƃ́A�����ɂ͍l�����Ȃ��������Ƃł����A�w�����Ɋw�����S�����W�߂Ă��������A�V�������Âł��邱�Ƃ�������A�������Ă������������Ƃɂ������ł��܂����B���ː搶�̎x�����Ȃ���ƂĂ��A�g��w�@�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������Ǝv���܂��B���ː搶����������Z���^�[�̑����ɂȂ��Ă���́A���X�d�b���������Ă��āA�ꏏ�Ƀr�[�������ދ@�����܂����B�搶���猩��A���q�����Â̂��Ƃ����l���Ȃ�����̋�������S�z���Ă����̂��Ǝv���܂��B�搶����͒Z�����Ԃ̂��w���ł������A������傫�Ȏ��_�ōl���邱�Ƃ��������܂����B
�@�������ɂ́A���ɑ����Č��@���̑���搶�ƁA�����ː��Z�p�Ȓ��̐{�ꂳ��ɎQ�����Ă�������̂ł����A��Â�搶�ɔC���A���u�W�͂��ׂĐ{��Ȓ��ɔC���܂����B�����A�o�c�I�Ɉ���ł���600 �����鑕�u�ɂ��Ă����悤�ɁA�{��Ȓ��̊�����邽�тɂ��邳�������Ă����̂ŁA�O�H�d�@���w�����Č��݂̂��炵�����u�ɉ��P�����Ă���܂����B����@���́A�Տ��ƂƂ��Ă������D��Ă���A���݂̈�ÃZ���^�[�̎����̓K���g��͔ނȂ��ł͂ł��Ȃ������Ǝv���܂��B�ނ�Q�l�ɂ́A�悭�A�h�o�C�X����܂������A�����Ƃ��Ȃ��Ƃ������A���̓s�x�A������ʂ��Ƃ������悤�ɂ��܂����B
�@���q����ÃZ���^�[�́A2009�N��636���̊��҂�������Â��Ă��܂��B�o�c�I�Ɉ��肷�鐔�ɂ悤�₭�B���܂����B�܂��A��t���[�����Ă���A�a�@�Ƃ��Čp���͂ł���ł��B���N�O����A�������ŗ��q�����Â�����v�悪����A�ψ��Ƃ��Ĉӌ��������Ă���܂������A���悢��{�݂��ł��邱�ƂɂȂ�A�ӔC�҂Ƃ��Ă��Ăق����Ƃ��������v��������܂����B��w�����̍���搶�ɑ��k���A����搶����p�҂Ƃ��ēK�C�ł��邱�Ƃ𗝉����Ă��炢�A�p���ł���ɂȂ������Ƃ�����A��������������āA�R�����ɑސE�����Ă��������܂����B�ސE�ɂ�����A��˒m�����疼�_�@���̎��߂����������܂������A��ό��h�Ɋ����A���ŐF�X�w���Ă�����������ɂ��̂悤�ɏ������Ă���������ϊ��ӂ��Ă��鎟��ł��B16�N�Ԍ��ɂ��܂������A�����̕�����F�X�Ȃ��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł������Ƃ�����̎{�݉^�c�ɐ��������Ƃ����ւ̉��Ԃ��ƍl���āA�S������w�h�ɕ��C��������ł��B
�@����20�N�S���ɒ��C�B�����g�A�a�@�Ζ��͂R�x�ڂł������A�O��12�N�Ƃ����Ό����o���A�a�@���Ƃ�����14�N�x����n�����c��Ɩ@�̑S���K�p���A�����Ɏ������g�̗����ʒu���傫���ς�钆�A��i��Â�S���Z���^�[�ɑ��āA�傫�ȃJ���`���[�V���b�N���o���܂����B
�@���ɁA���q�����ẤA�����̒��ł́A����܂ł̈�w�̏펯������I�Ȃ��̂ł����B���ẤA�u�O�ȗÖ@�i��p�j�v�u���w�Ö@�v�u���ː��Ö@�v�̂R���嗬�ł����A���q�����ẤA���q���̎��u���b�O�s�[�N�Ƃ����������������āA������s���|�C���g�ŎE������ƂƂ��ɁA�]���̕��ː����Âɔ�ׁA���̐���g�D�ւ̉e���A����p�����������Ȃ��ȂǁA���҂���̑����̎Љ�A���\�Ƃ�����ɗD�������Ö@�ł����B
�@���������r���𗁂т�\�̕����̈���ŁA���q�����ẤA���a30 ���́u����V���N���g�����v���u�̌̏Ⴊ����������A�S�Ă̎��Â��X�g�b�v����Ƃ����傫�ȉۑ������܂��B�K���ɂ��āA����܂łX�N�ԁA�����������Ԃɑ������܂���ł������A��ɋْ����������āA���u�ێ�ɓO����X�^�b�t�̓��X�̐^���Ȏp���E����J�ɂ́A�{���ɓ��̉�����v���ł����B
�@���݁A���{�����ɂ����āA���q�����Â��s���{�݂͂V�J����������܂���B23 �N�ɂ͂Q�J���V�݂����\��ł����A�z�q�A�Y�f�̗��j����g�p�ł���{�݂́A���Z���^�[�����E�B��ł���A��ɒ��ڂ���Ă���{�݂ł��B����15�N�x�����ʐf�Â��X�^�[�g���A����250�l�ł��������Ґ����A21 �N�x�ɂ͏��߂�600 �l�̑����A�߂������̍���������������ттĂ��܂����B�������A�����Ɏ���܂ł̊j��ؑւ̎��ԒZ�k�A���u�̕ێ番�U�Ȃǂ̋Z�p�I�Ȑςݏd�˂ƂƂ��ɁA��ÃX�^�b�t�̈�È��S�ɑ���ӎ���Ɩ��������̓O�ꂪ�A�������������̎��Â��\�ɂ������ƍl���Ă��܂��B
�@�����g�A�������̃g�b�v�Ƃ��Čg���܂������A�Z���^�[�̎���́A�����܂ł���t���͂��߂Ƃ����ÃX�^�b�t�Ǝ��ÏƎ˂̗v�ƂȂ�Z�p�X�^�b�t�̗��ւ����S�ł����āA���������X�^�b�t�S���ɂ��`�[����Â̂��ƁA�����Ղ����Â������{�Ƃ��āA�����E�Ƃ��Ă̖����A�ւ�����͍������Q�N�Ԃł����B
�@����ŁA�u36 ����̒����v�u�������v�u���z�ޗ��̔�p�����v�ȂǁA���Ă̎�����̎�����ƂɌg���A�@���O�̏������ň݂��`�N�`�N���鎞��������܂������A��J�̍b�オ�����āA���Ƃ��܂Ƃ߂�グ�邱�Ƃ��ł��܂����B������ЂƂ��ɂ����͂����������X�^�b�t�̂��A�Ɗ��ӂ��Ă���܂��B
�@���A�U��Ԃ�ƁA���t���Ԃ��Ȃ����葱���A���g�̔Z���Q�N�Ԃł����B�������Ƃ��āA���q�����ÂƂ����Ő�[�{�݂ɂ����āA���ł͌o���ł��Ȃ��悤�ȋM�d�Ȍo�����ł������Ƃ�������v���ƂƂ��ɁA����Ƃ��A�Z���^�[�����[�f�B���O�{�݂Ƃ��Ă��葱���A�v�X���W���邱�Ƃ��A�A�Ȃ��牞���������Ǝv���Ă��܂��B
 |
| H21�N�S�����C���̃j���[�X���^�[��28���ł́u���Î����̊g��ɑ������Ō�Ȃ̎��g�݁v�Ƃ��āA�@�N���j�J���p�X�̐ϋɓI���p�ƃ`�[����Â̐��i�@�A�n��{�݂Ƃ̘A�g�Ƒމ@��̃t�H���[�A�b�v�V�X�e�������グ�܂����B����͂P�N�Ԃ̐i�������m�点���A���q����ÃZ���^�[�̔��W�Ɋ肢�����߂ĊŌ�Ȃ̖����\�z�}��`���Ă݂܂��B |
|
 |
�yQOL �ɒ��Ⴕ���`�[����Â̐��i�z
�@H21�N�x�A�Z���^�[����ۂɂȂ��Ď��g�̂��u���������Áv�ł��BH21�N�x����R����܂Ƃ̕��p���Â��J�n����܂����B�ƎˑO�̈��H�����E�R����܂ɂ�镛��p�Ǐ�E�����ԁi1.5 �����j�ɂ���ԏƎ˂Ƃ���ɔ����s���E�X�g���X�́A��X�̗\�z���͂邩�ɒ��������̂ł����B
�@���҂���̎��Ì��ʂ����߂���QOL ��ቺ�����Ȃ����߂ɁA�Ō�t�E��t�E���ː��Z�t�E��t�E�Ǘ��h�{�m�E�����Z�t�E��w�����m�����u��ÂƂ��Ēł��邱�Ɓv���c�_���A���ꂼ�ꗧ��ƐӔC�̂��Ƃɍő���ł��鎖���H�v���W�J���Ă��܂����B�H�����e�̍H�v�E�h�{�]���ƕ⏕�H�i�̓����E�Ǝˎ��Ԃ̍l���E����p�y���̂��߂̓K�Ȗ�܂̑I�ł��B���ɊŌ�t�́A���҂̗���ɗ����Đ������ʂ��瑽�E��֓��������A�E��Ԃ̃R�[�f�B�l�^�\�Ƃ��Ă̖��������ɓw�߂܂����B
|
|
|
�y�n��{�݂Ƃ̘A�g�ƃt�H���[�A�b�v�V�X�e���z
�@H21 �N�x�ɓ���A�A�g�a�@�Ƃ��ĐV���ɂP�{�݂������܂����B������̕a�@�E���֗��q�����ÁE�Ō�Ɋւ���u�`�̊J�Â�Ō�t���Z���^�[���ɏ��������n���C���s���������܂����B���҂���́A�u���Ñ҂����Ԃ̒Z�k�v�u���@�{�݂���ʉ@�ł��Ĉ��S���v�u�A�g�{�݂𗘗p���銳�ғ��u�̌𗬂��ł���v�ȂǍD�]�ł��B
�@�܂��A���ÏI����̊��҂���ƃZ���^�[�����ԊŌ�t���R�A�ɂ����u�t�H���[�A�b�v�T�|�[�g�V�X�e���v�ɂ��d�b���k�⊳�ҁ|�厡��\���q����ÃZ���^�[�Ԃ̒����́A���Ð��̑����Ƌ��ɂ܂��܂��j�[�Y���������Ă��܂��B
�@�^�C�����[�ɑΉ��ł���悤�ɁA�̐��̌����������ۑ�ł����A�����e���r�d�b���̒ʐM�@�����g�������u�Ō삪�ł���������邱�Ƃ�����Ă��܂��B
|
|
 |
�@�g 21 �N�x������{�Ō싦��ɂ����āu������ː��Ō�F��Ō�t�v����ے����J�u����܂����B11 ���ɂ͑�P����30 �����u���q�����Î{�݂̌��w�ƊŌ�̎��ۂ��w�ԁv�ړI�Ō��w���C�Ɍ}���A�𗬂���@��������܂����B���̑��A�l�X�ȊŌ��w�◱�q���{�݂���w����Ō�t�̎{���w�������A���q�����Ẫp�C�I�j�A�{�݂Ƃ��āA�Ō�Ȃ����̂悤�ȋ@���ꂽ���Ƃ��όւ�Ɏv���Ă��܂��B
�@�u������ː����Ái���q�����Áj�v�̓��f�B�A�̉e�������肪�҂̊��҂������A����܂��܂��L�������̐l�X�ɗ��p�����悤�ɂȂ邱�Ƃł��傤�B���ÁE�Ō�̎��т�����������A�l�X���������I���Ɩ����ł����Ê��̒��ł�莡�Ì��ʂ��オ��悤�ɁA�n�[�h�E�\�t�g�ʂ̔��{�I�ȕϊv�������Ă��܂��B
�@�J�@10 �N�ڂ̐ߖڂɍ������ǁA�u�a�@�̗��O�v�ɗ����߂�A�ω����Ă������ґw�ƈ�Ãj�[�Y�̎��_�ŁA�g�ϊv���ׂ����Ɓh�g��邬�Ȃ���Ɉێ����ׂ����Ɓh�͉��Ȃ̂����čl���A���q�����Á��Ō�̑�Q����Ɉڍs���邱�Ƃ������Ă���Ǝ������܂��B
�@�u���m�v�������҂���ɗE�C�Ɗ�]�������Ă����������߂ɁA���̎���ɂ����Ă��Ō�Ȃ̃��b�g�[�ł���u��Ɋ��҂���Ƌ��ɂ���Ō�v�M�������邱�Ƃ����Z���^�[�Ō�Ȃ̎g���ł��B
�@�X������͔�r�I�p�x�̒Ⴂ�a�C�ł����A���Ɉ����x�������A���u�]�ڂ��N�����₷������ł��邽�߁A�������̑�\�Ƃ���Ă��܂��B�܂�����ɂ��X�����̂��ג����ď����ȑ���ł��邱�Ƃ���A����̑傫�����܂��������������X���̊O�֍L�����Ă��܂��A���Ƃ��������X��������邱�Ƃ��ł����Ƃ��Ă���p�Ŏ��邱�Ƃ�����ȏꍇ���łĂ��܂��B���{�ł́A�������Ɏ�p�ɂ���Đ؏����ł���Ɣ��f������X����͑S�̖̂�20���ɂƂǂ܂�܂��B���̑��̂���Ɣ�r����Ƃ��܂�ɒႢ��p���ł���ƌ��킴��܂���B
�@��p�̂ł��Ȃ��X����ɑ��Ă͈�ʓI�ɍR����܂ɂ�鎡�Â��s���܂����A�����_�ɂ����Ă͍R����ܒP�Ǝ��Â͌����Ė����̂ł��錋�ʂł͂���܂���B���̂悤�Ȏ�p�s�\�X����ɑ��ẮA�ȑO����R����܂�X ���ɂ����ː����Âp�����u���w���ː��Ö@�v���������s���Ă��܂����B�����̒��ɂ͍R����ܒP�Ǝ��ÂƔ�r���ėǂ����Ì��ʂ�����ꂽ�Ƃ�������������܂����A�����̎��ÂŔ�r�ΏۂƂȂ�R����܂����Â��^�C�v�̂��̂ł���A���ݎ嗬�Ƃ��Ďg�p����Ă��鉖�_�Q���V�^�r���Ƃ����R����܂Ɣ�r���ꂽ�f�[�^���قƂ�ǂȂ����߁A�����ɂ����Ắu���w���ː��Ö@�v�͕K��������p�s�\�X����ɑ��鎡�Ö@�̎�̂Ƃ͂Ȃ��Ă��܂���B�ŋ߂ł͂��̐V�����R����܂ł��鉖�_�Q���V�^�r����A�e�B�[�G�X�����Ƃ��������̍R����܂�X �����Âp�������w���ː��Ö@�̗Տ��������������s���Ă���A�R����ܒP�Ǝ��ÂƔ�ׂĂ�荂�����Ì��ʂ�������̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂���Ă��܂��B
�@���Ɍ������q����ÃZ���^�[�ł́A2008 �N�x��艖�_�Q���V�^�r���Ɨ��q�����Â��ɕ��p���鎡�Â�Տ������Ƃ��čs���Ă��܂��B����͍��c�@�l�Ђ傤���Ȋw�Z�p����̏��㌤�������Ă���A���̐��ʂ����҂���Ă��܂��B
�@�X���͎��͂��݂�\��w���A�����A�咰�Ȃǂ̏����ǂɈ͂܂�Ă��邽�߁A�X�����X�����Ǝ˂��悤�Ƃ���ꍇ�ɂ͂ǂ����Ă����������ǂɂ�X�����Ǝ˂���Ă��܂��܂��B�����ǂɂ��܂葽����X�����Ǝ˂���Ă��܂��ƈݒ�ᇂ�\��w����ᇁA�����Ǐo����Ђǂ����͏����ǐ��E���������ꍇ������܂��B�����͏ꍇ�ɂ���Ă͒v���I�ȕ���p�ƂȂ�܂��B�����ŁA�����ǂ̑ς�������ʂɂ����X�����X����ɑ���Ǝː��ʂ����܂��Ă��܂��A50�O���C���x�����E�ƂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���q����X���ƈႢ�u���b�O�s�[�N�Ƃ������ɗD�ꂽ�����������߁A�����ǂւ̏Ǝ˂�50�O���C�ɗ}���Ȃ�����X����ɑ��Ă�70�O���C�O��܂ŏƎ˂��邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B����ɂ���Ă���ɍ������Ì��ʂ����҂��邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���q�����ÂƓ����ɍR������Âp���邱�ƂŁA�R����܂ɂ�闱�q�����Â̍�p�������ʂ�A�����̔����ȉ��u�]�ڂɑ��Ă̓������̎��Â��\�ɂȂ邱�ƂȂǂ̃����b�g�������܂��B
�@���̂悤�ɗ��_��͔��ɗD�ꂽ���Âł���ƌ�����̂ł����A���ۂ̈�Âɂ͗\�z�O�̎��Ԃ�������ꍇ������܂��̂ŁA���ݐT�d�Ɏ��Ì��ʂ╛��p�ɂ��Č������s���Ă���Ƃ���ł��B
�@���Z���^�[�ł̎��Âɂ�������Ԃ͖�T�T�Ԃł��B���̊��Ԓ��ɉ��_�Q���V�^�r�����R��_�H���܂��B���܂Ŏ��ۂɊm�F���ꂽ����p�Ƃ��āA�H�~�����A�̏d�����A�q�C�Ȃǂ̏�����Ǐ��A�ݒ�ᇂ�����Ǐo���Ȃǂ̔S����Q������܂��B�����̕���p�͂�����x�����Ă͒ʂ�Ȃ��̂ł����A���q�����Â̍H�v�A�R����܂̓��^�@�̍H�v�A������H���̍H�v�ɂ���ď��X�ɕp�x�͒ቺ���Ă��Ă��܂��B���Ì��ʂɂ��Ă͓�������\�z����Ă����悤�ɁA�X���̂��̂ւ̎��Ì��ʂ͔��ɍ����A�ꍇ�ɂ���Ă͎�p�ɕC�G����悤�Ȍ��ʂ������Ă��܂��B�������A�X���ȊO�̑���A���Ƃ��Ί̑��ւ̉��u�]�ڂȂǂ����ɂȂ�ꍇ������܂��̂ŁA���Z���^�[�ł̎��Â��I��������������̊��ԁA�R����ܒP�Ƃɂ�鎡�Â𑱂��Ă������Ƃ��d�v�ł���ƍl���Ă��܂��B�܂��A���q�����Â��s�����ɂ�������炸�X���̂��̂��Ĕ����Ă��܂��ꍇ������܂��̂ŁA���コ��Ɏ��Õ��@���H�v�����ʂ����߂Ă��������ƍl���Ă���܂��B
|

